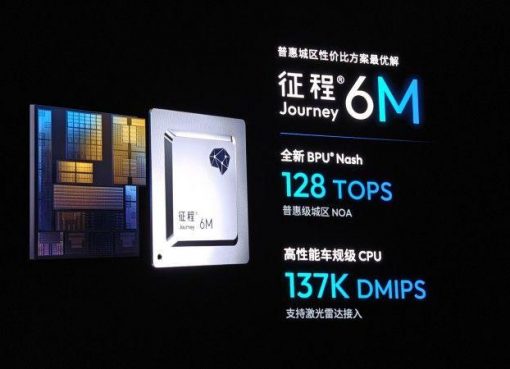原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
中国ネット大手の百度(バイドゥ)傘下で自動運転タクシー(ロボタクシー)を展開する「蘿蔔快跑(Apollo Go)」が、米テスラなどライバルに対抗するため、LiDAR技術を捨て、カメラのみに頼るピュアビジョン方式へ舵を切ると報じられた。
バイドゥの李彦宏(ロビン・リー)会長兼CEOは経営会議で、「ロボタクシーをピュアビジョン方式に切り替えない限りチャンスはない」と述べ、テスラがピュアビジョン技術を確立させる前に機先を制さなければ、市場での主導権を失ってしまうと強調した。

現在主流となっている自動運転レベル4のソリューションには、LiDARやカメラ、ミリ波レーダーなどさまざまなセンサーが使用されている。バイドゥをはじめ、米Alphabet傘下のウェイモ(Waymo)や中国の小馬智行(Pony.ai)、文遠知行(WeRide)などトップ企業はいずれもこの方式を採用している。一方、現時点でピュアビジョン方式を採用しているのはテスラのみ。同社の自動運転ソリューション「FSD(フルセルフドライビング)」はセンサー類を一切使用せず、データの検証時にLiDARを補助的に使うだけだ。
Apollo Goは2021年に商用運行を開始してから2025年5月までに、北京市、湖北省武漢市、重慶市、広東省深圳市、上海市などで延べ1100万回以上サービスを提供している。
バイドゥが今回ピュアビジョン方式を選択したのは、ハードウエアのコストを削減し、大規模展開を進めるためと考えられている。LiDARのコストは2018年の数万元(数十万円)から、現在では中国製で約3000元(約6万円)ほどに値下がりしたとはいえ、技術改良のサイクルが速く、一度構築したシステムを長く使用するのは難しい。これに比べるとカメラは本体そのものが安いことに加え、データのタグ付けやシステム汎用化のコストでもメリットが大きい。
Apollo Goが展開する第6世代の自動運転車は販売価格20万4600元(約430万円)で、第5世代に比べ約60%安くなった。しかし李CEOは、将来的にロボタクシーの利用料金を現在のタクシー料金の半分にすることを目指しており、そのためには車両コストのさらなる削減が不可欠になる。ピュアビジョン方式の実現は目標達成のカギを握っている。
バイドゥはピュアビジョン方式の開発にゼロから取り組むわけではない。初期のApolloシステムは、BEV(Bird’s Eye View、鳥瞰図)アルゴリズムと視覚占用ネットワーク(Occupancy Network)、深層学習モデル「Transformer」を組み合わせた視覚ソリューションを使用しており、量産車に搭載してテストも実施されている。さらにこれまでロボタクシーが蓄積してきた6000万キロメートルを超える走行データも、ピュアビジョン方式の実用化に大いに役立つ。

ただ、過酷な天候や複雑な地形など特殊な条件下では、センサーを併用するソリューションに軍配が上がる。テスラのFSDバージョン13は複雑な条件下でのパフォーマンスが向上したが、それでも低照度の環境では依然として限界がある。このため、Apollo Goがピュアビジョン方式にシフトすることでどの程度の効果がもたらされるのか、しばらく状況を見守る必要がある。
作者:車東西(WeChat公式ID:chedongxi)、頤聖
※1元=約21円で計算しています
(翻訳・36Kr Japan編集部)
原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録










 フォローする
フォローする フォローする
フォローする