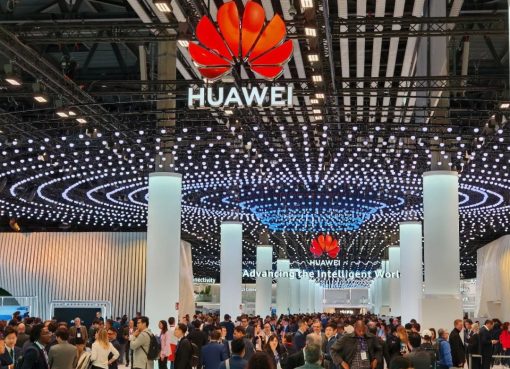原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
米調査会社IDCのデータによると、2023年の世界スマートフォン出荷台数は、前年比3.2%減の11億7000万台だった。世界的なインフレや在庫の積み上がりなどの影響により、過去10年で最低の水準となった。
メーカー別では、米アップルが初めて韓国サムスン電子を抜き、首位に立った。3〜5位は中国メーカーの小米(シャオミ)、OPPO(オッポ)、伝音控股(トランシオン)だった。
スマホの買い替えサイクルが長期化する中、どのように売り上げを伸ばし続けるかが、中国メーカーにとって喫緊の課題となっている。昨年のChatGPTに代表される大規模言語モデル(LLM)の世界的なブームは新たな希望をもたらし、メーカー各社はスマホへのLLM導入に着手した。
先陣を切ったのはファーウェイ(華為技術)だ。昨年8月に、独自オペレーティングシステムのHarmonyOS 4にLLM「盤古」を導入すると発表したことで、スマホ業界に人工知能(AI)の風が吹き始めた。
昨年10月には、シャオミが独自開発したLLM「MiLM-6B」にXiaomi Hyper OS(澎湃OS)が組み込まれ、AIアシスタントの「小愛同学」がテキスト作成、画像加工などの能力を備えたと発表。続く11月にはまずvivoが独自開発のLLM「藍心大模型(BlueLM)」をリリースし、次にOPPOがColorOS 14にLLM「安第斯大模型(AndesGPT)」を組み込んだ。Honor(栄耀)も今年1月、70億パラメーターに対応する独自開発LLM「魔法大模型」を発表している。
OPPOは今年2月に、さらに新たなAI事業戦略を発表した。スマホのAIエージェントをリリースしただけでなく、AI エージェント開発プラットフォームを立ち上げ、AIプラグインの提供を通じて開発者と共同でエコシステム構築を目指す。劉作虎CPO(最高製品責任者)はAIについて、同社が上限なしに投資する重要な技術研究分野になるとの考えを示した。
同月には大手を追走する新興メーカー魅族(Meizu)が、従来のスマホ開発を止めて新しいAIデバイスの開発に転じる方針を発表した。目指しているのは米Humaneやrabbitといった新しいAIデバイスメーカーで、「All in AI」のコンセプトを打ち出している。
中国メーカーだけでなく、あまり目立たなかった米アップルにも動きがあるという。著名アナリストの郭明錤(ミンチー・クオ)氏によると、次世代の「iPhone 16」はアップルにとって初のAI搭載スマホになる見通しだ。
LLM利用シーンは同質化、ビジネスモデル確立が必要
現時点で、LLMの導入はスマホメーカーにとって、収益を生み出していないどころか、コストを大きく増やしている。端末のメモリ、チップ、GPU性能の要件が高くなり、スマホの平均販売価格は大幅に上昇した。
LLMの処理を端末ではなくクラウド上で行おうとしても、多くのユーザーを抱えるメーカーの演算処理コストは恐ろしいほどに膨れ上がる。例えば、OPPOは2024年の春節前夜にAI機能を1000万人のユーザーにプッシュしたが、それを支えるための演算処理コストはユーザー1人当たり数元(数十~百数十円)かかり、総額1000万元(約2億1000万円)以上に上った。
業界関係者の試算によると、LLMの演算処理をクラウド上で行う場合のコストは最低0.012元(約25銭)で、3億人のユーザーが1日に10回使うと、スマホメーカーは年間100億元(約2100億円)以上を負担しなければならない。特に米OpenAIが動画生成AI「Sora」を発表したことで、今後はLLMが次第にテキストや画像から動画の分野へと移行し、求められる演算能力がさらに高まると見られる。
従ってメーカーはスマホにLLMを導入後、どのようなビジネスモデルを確立し、収支のバランスを取るかが検討すべき課題となる。
また、現状を見ると、スマホでLLMを利用するシーンは似たり寄ったりだ。一般的なスマホに導入されたLLMの利用シーンは基本的に画像、通話、音声アシスタントの範囲に収まる。例えば、画像をめぐる機能では加工や修正、検索が一般的だ。通話においては、通話時のリアルタイム翻訳や情報のリアルタイム記録がある。音声アシスタントはもっと似通っており、基本的にAIエージェントがテキスト生成、テキストから画像生成、対話、情報検索などの機能を提供する。

今のところこうした機能は使用感の向上を目的としており、当面はユーザーから料金を取ることは難しそうだ。一方、ユーザーからAI機能の料金を取るのではなく、スマホの使用感を改善することで早期の機種変更を促すという考え方もある。
IDCは以前にも、AI搭載スマホが買い替えの波を起こす可能性があると予測していた。AI搭載スマホは2024年に3700万台が出荷され、27年までに市場全体に占める割合が50%を超える見込みだという。
千里の道も一歩から。長い目で見ると、AIはこれまでにないインタラクション、アーキテクチャ、アプリ提供をけん引していくことになる。スマホメーカーはLLM搭載競争に突入するが、結局は自己革新する勇気を試されることになるだろう。
*2024年3月31日のレート(1元=約21円)で計算しています。
(翻訳・大谷晶洋)
原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録







廃棄物を資源に 江蘇省が循環経済の発展推進XxjjpbJ007032_20250704_CBPFN0A001538.jpg)

BYDブラジル工場で最初の1台が完成XxjjpbJ007149_20250703_CBPFN0A001868-scaled.jpg)


 フォローする
フォローする フォローする
フォローする




廃棄物を資源に 江蘇省が循環経済の発展推進XxjjpbJ007032_20250704_CBPFN0A001538-510x369.jpg)

BYDブラジル工場で最初の1台が完成XxjjpbJ007149_20250703_CBPFN0A001868-510x369.jpg)