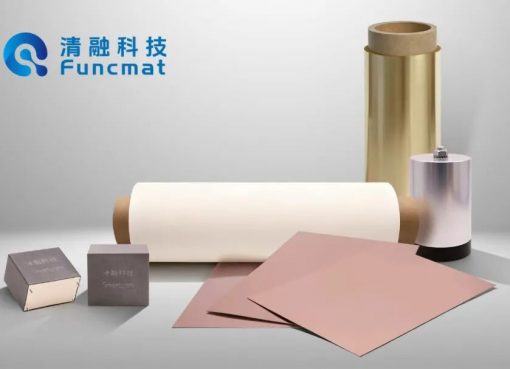原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
スマホ・IoT家電大手のシャオミ(Xiaomi、小米)が、新型コロナ禍のため4カ月間延期していた10周年記念大会を開催した。創業者の雷軍CEOは、シャオミの10年間の歴史を振り返り、そして新商品を発表した。
シャオミの創業メンバーは大半がすでに会社を離れ、強力なライバルも続々と出現している。10年間で世界トップ500に成長したシャオミだが、まだ安心できる状態にはない。
開発に注力するも茨の道
これまで、シャオミについては、販売力は素晴らしいが、技術力は中途半端という評判がついて回っていた。そのため、雷軍CEOは記念大会で再度「2020年の開発費は100億元(約1500億円)超」と強調し、シャオミが開発に注力しはじめたことを印象付けようとした。
財務データを見る限り、シャオミの開発費は確かに増えている。2015〜2019年の年間開発費は、それぞれ15億元(約230億円)、21億元(約320億円)、32億元(約480億円)、58億元(約870億円)、70億円(約1100億円)である。例年の伸び率でいえば、今年100億元(約1500億円)超となっても大幅な増額とはいえない。唯一評価できるのは、新型コロナ禍による販売減でも、開発費の増加ペースが鈍らなかったことだ。

すでに大企業となったシャオミが、重心を開発に移そうとしても、それは容易なことではない。ファーウェイ傘下の半導体メーカー「海思(HiSilicon)」が現在の開発力を身に付けられたのは、長年の積み重ねと、ファーウェイの収益力により潤沢な予算を確保できたことによる。それに対し、シャオミのハードウェア販売の粗利率は5%未満であり、インターネット事業とIoTサービス事業の売上高が伸びるまでは、開発を強化しようとしてもその余力がないのである。
もちろん、厳しい状態の中でも、シャオミは技術面で一定の進歩を遂げてきた。たとえば、ハイエンド機種「Mi 10 Pro」のカメラ機能は、ベンチマークサイト「DXO Mark」で世界トップの評価を得ており、また10周年記念機種の「Mi 10 Ultra」はグラフェンバッテリーを初採用している。記念大会ではさらに、世界初の量産化された透明OLED(有機発光ダイオード)テレビを公表した。販売価格は49999元(約76万円)から。
しかし、これらの先端技術の認知度は低く、スマホの機能の高さという面で、消費者がシャオミの名を挙げることはまだ少ない。シャオミが今から本格的に技術開発を進めても、そのイメージが定着するまでには時間を要すると思われる。
コスパも諦めないシャオミ
コスパの良さで売り上げを伸ばしてきたシャオミは、今もこの最強の武器を手放していないが、その内容はやや変化した。スマホ、テレビなどの新製品を見ると、低価格一辺倒ではなく、他社に劣らぬハイエンドモデルを比較的安い価格で提供することにこだわっている。
しかし、消費者はシャオミにそのようなイメージを持っていない。今年のMi 10と「Redmi K30」が、発売後まもなく価格切り下げとなったことが、それを裏づけている。
それでは、シャオミはどうすればよいのか。雷軍CEOが記念大会で語ったのは、「世界最高の品質を持つ製品を提供する」という点であった。いわば基本に立ち返った形だが、同氏が続けて認めたように、「品質を上げることは非常に手間と時間がかかる」のである。
10年前の雷軍氏は、コスパ重視の道を選び、10年間の成功につなげた。今後はそこに技術、デザイン性を加えていくことになるが、10年前よりも難しい道のりになりそうである。
(翻訳:小六)
原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録








世界初のハイブリッド大型無人輸送機、重慶で初飛行に成功XxjjpbJ000175_20260203_CBPFN0A001986-scaled.jpg)




 フォローする
フォローする フォローする
フォローする
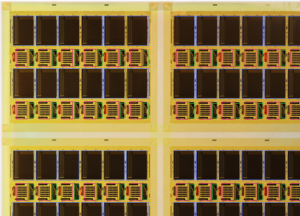



世界初のハイブリッド大型無人輸送機、重慶で初飛行に成功XxjjpbJ000175_20260203_CBPFN0A001986-510x369.jpg)