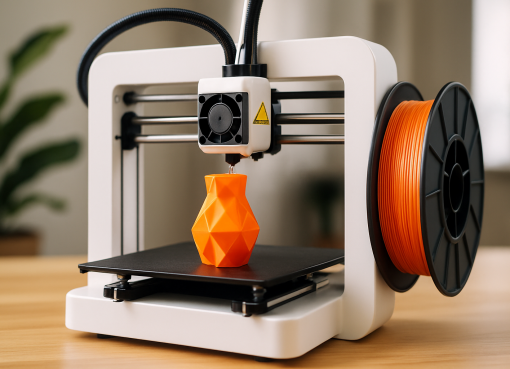36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。
原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
中国の自動運転技術のスタートアップ企業「恵爾智能(Whale Dynamic)」は、自社開発の小型無人車の商用化を進めている。
恵爾智能は2017年に設立され、5年以上にわたり技術開発を進める中で、徐々に自社の路線を定めていった。レベル4の乗用車向け自動運転技術を足がかりに、公道を走れる小型無人車両を開発し、これをクラウドサービスと抱き合わせで販売する。主要ターゲットは欧米、中東、日本、韓国などだ。
創業者の常宇飛氏は、ロボタクシー(無人運転タクシー)やロボトラックに比べて、小型無人車両の難易度はそれほど高くもなく、コストコントロールの面でも有利だという。とくに欧米諸国では都市部と地方の格差が比較的小さく、道路状況も均質化が進んでいるため、単一のモデルを国中に適用できる可能性が大きい。独自にフルスタック開発したレベル4の自動運転技術を基礎に、一から開発を進めた。まず乗用車向けのアルゴリズムを検証して、シャシ・バイ・ワイヤーのアルゴリズムを編み出し、最終的に公道を走れる量産型の無人車両に活かした。
同社は日本や韓国などアジア諸国の市場視察も進めており、数カ国で小型無人配送車の仮発注も獲得したという。また、無人配送車両の量産や人材募集、チャネル開拓に充てるため、近く新たな資金調達を予定している。
(36Kr Japan編集部)
36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。
原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録











 フォローする
フォローする フォローする
フォローする