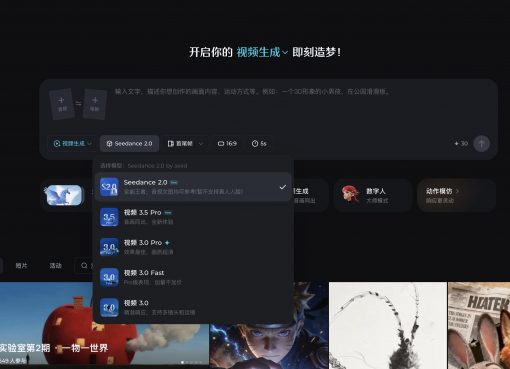セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
中国・広州に本拠地を置く国有自動車大手「広州汽車」が、2026年中に日本で乗用車を発売する。日本展開の鍵を握るインポーター「M Mobility Japan」に投入予定の車種や今後の展望について話を聞いた。
広州汽車は広州市政府が所有する自動車メーカーで、企業グループとしての「広州汽車集団(GAC)」は1997年に誕生した。広州市における自動車製造の歴史は1954年まで遡り、同年に路線バスの修理工場「広州市公共汽車修配廠」が自ら初のバスを完成させた。
中国における乗用車の製造は、ときの最高指導者である鄧小平氏が1970年代後半から主導した「改革開放」政策により大きく前進した。外資を積極的に取り入れることで日本やアメリカ、ドイツ、フランスの自動車メーカーを中国へ誘致。中国各地の自動車メーカーとの合弁会社設立を通じて現地生産を進め、中国の自動車製造能力は飛躍的に向上した。広州市政府も1985年にフランスのプジョーと合弁「広州プジョー」を設立、「天津ダイハツ」や「上海フォルクスワーゲン」、「北京ジープ」などと並ぶ初期の自動車合弁事例の一つとされる。
一方、広州プジョーは、現地サプライヤーとの良好な関係構築に失敗し、品質問題が露呈した。合弁関係は12年間続いたのちに解消され、広州市政府は次なる合弁パートナーとして日本のホンダを選び、こうして「広州ホンダ(現・広汽ホンダ)」が誕生した。1997年のGAC設立後も、いすゞや日野、三菱、フィアット・クライスラー(現・ステランティス)などと合弁を設立したが、現在存続しているのは広汽ホンダとトヨタとの「広汽トヨタ」が中心となっている。
自主ブランドの苦戦と海外展開の強化
GACは2025年に合弁車種含むグループ全体で172万1000台を販売。そのうち自主ブランドは約61万台だった。この規模は、奇瑞汽車(263万台)」、吉利汽車(302万台)、BYD(460万台)など、同程度の歴史を誇る他社と比べると少ない。
自主ブランドは「広汽傳祺汽車」が展開する「トランプチ」や、「広汽埃安新能源」の「アイオン」や「ハイプテック」などがあるが、前年比でプラス成長を記録したのは広汽トヨタ(+2.44%)のみ。ほかはすべて22〜25%のマイナスとなった。グループ全体の販売台数や前年比成長は伸び悩んでいる一方、四半期ベースを見ると、3期連続で前期成長率プラスを見せた。需要の変化や激しい価格競争の中でも、なんとか改善している傾向と言える。
海外事業では2025年は前年比47%増の13万台を販売した。新たに16市場へ進出し、合計で86の国と地域に拡大した。マレーシアではノックダウン生産の工場も稼働したばかりで、ほかの中国勢に遅れをとりながらも海外展開を強化している。
日本進出のキーマン「M Mobility Japan」
そんなGACが次に目指すのが日本だ。インポーターとして日本事業を手伝うのは2024年に設立された「M Mobility Japan」で、新興EVメーカー「NIO」の共同創設者としても知られる鄭顕聡(Jack Cheng)氏がトップを務める。同氏は1981年に米・フォードの自動車を台湾で製造や販売する「福特六和汽車」に入社後、アメリカやオーストラリア、イギリス、そして中国の現地法人を渡り歩いた。
フォード退社後はイタリアのフィアットに移籍し、2010年には広州汽車との合弁「広汽フィアット」のトップに就任した。M Mobility Japanが広州汽車を扱うのはこのときの繋がりから来ているとのこと。台湾の鴻海(フォックスコン)が主導するEVコンソーシアム「MIH」のCEOも勤めたが、2024年に退社してM Mobilityを台湾と日本の両方で立ち上げ、今に至る。
未だ謎の多いM Mobilityだが、今回は広州汽車の日本進出戦略について、同社の広報を担当する陳春帆(Fan Chen)氏に話を聞いた。
中国EVミニバン「ZEEKR 009」が日本上陸、社長車や富裕層インバウンドに照準 フォロフライ1300万円から輸入で提供
第一弾は小型BEV「アイオンUT」
最初に日本へ導入されるのは、「アイオン(埃安、AION)」ブランドの最新小型BEV「UT」だ。のちにコンパクトSUV「V」も予定される。まずはUTをカーシェアやオートリース会社向けに導入し、そこで多くの人に体験してもらうことを狙っている。その形で2026年に200台、そして2027年には販路を拡大して2000台を目指す計画だ。

発売当初は年間の登録台数が5000台以下を見込まれる場合のみに適用できる「輸入自動車特別取扱制度(PHP)」を用いることで、本来必要な型式認証が簡略化できる。2023年より日本で乗用車販売を開始するBYDも当初はPHP制度を利用していたが、その後の販売拡大を見越して正式に型式を取得しており、M Mobilityも将来的には同じ流れになるだろうとのこと。
UTは全長4270×全幅1850×全高1575 mm、ホイールベース2750 mmのコンパクトな5ドアハッチバックで、同じBEVとしてBYDの「ドルフィン」に真っ向から勝負を挑む形となる。
輸出仕様のバッテリーは容量44.1 kWh(一部では50.2 kWh)もしくは60 kWhのリン酸鉄リチウムイオン電池の2種類で、これもBYDドルフィンとほぼ同じ仕様となる。一方でWLTCモードでの一充電航続距離はそれぞれ330~350 kmか420 kmと公表しており、この点に関しては415 km/476 kmのBYDドルフィンよりも劣ってしまう。全幅もドルフィンの方が1770 mmと小さく、狭い路地や機械式駐車場での運用はそちらに分がある。
日本発売にあたって具体的な仕様はまだ広州汽車が検討を進めている段階だが、ひとまず右ハンドルと日本で広く普及している急速充電規格「CHAdeMO」への対応はマストとしている。先行して同じアイオンの小型BEV「Y Plus」を日本に2台輸入し、公道を走るためのナンバープレートも取得しているが、充電規格は主に欧州で採用されている「CCS2」であるため、充電が少し煩雑だという裏話も語ってくれた。

試験的に輸入されたY Plusは中古車販売店「ガリバー」を運営、その販売網を活かしてアイオンを販売する「IDOM」のイベントでも展示された。来場者からは未来的な外観や室内空間の広さ、そして大きいセンターディスプレイといった点が評価されたとのこと。
現時点で決定しているディーラーはIDOMのみ。テスラのようなオンライン中心の販売ではなく、BYDに近い対面販売を主軸にするとしており、IDOMが運営する全国約460のガリバー店舗がここで強みとして活きる。BYDは2026年1月末時点で全国50カ所に正規ディーラーを設けており、陳氏はなかなか真似できることではないと、そのやり方に賞賛の言葉を送った。
マーケティングに関して陳氏にうかがったところ、意外な返答が返ってきた。てっきり宣伝や販促から広州汽車の色を消すと思っていたが、実際はその反対で、広州汽車のブランドであることを前面に出すとのこと。ターゲットは30〜40代の輸入EVに拒否感が無い消費者層で、受け入れてもらえる人にだけ売っていくようだ。
陳氏によれば、広州汽車の強みはトヨタやホンダとの合弁経験で培った品質の良さがアピールポイントで、これまでに140万台のEVを販売してきたものの、重大な発火事故は1件も起きていないと言う。日本での販売価格はまだ公表できないが、この確かな品質と先進性を武器に市場へ売り込みをかけていくとしている。
日本市場という難関
同じ中国勢のBYDとは規模が大きく異なるが、新たなプレーヤーが日本市場に進出するのはとても興味深いと感じる。一方、単に「電動化が遅れている」だけで片付けられるほど日本市場は単純ではなく、広く浸透を目指すのであれば、日本勢のハイブリッドと勝負することとなる。その点はM Mobilityも理解しているようで、そういった車種と勝負するのではなく、少しでも新たな選択肢を市場で増やし、小規模ながらも電動化を進めていくという気概を感じた。
(中国車研究家・加藤ヒロト)
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録













 フォローする
フォローする フォローする
フォローする