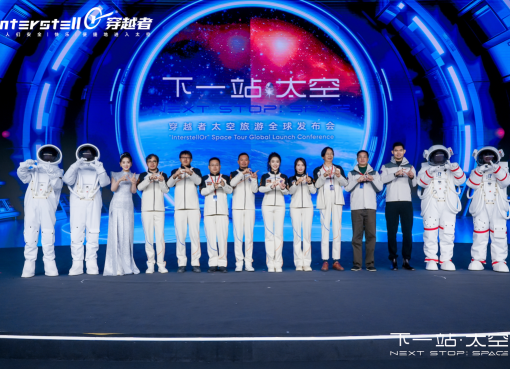原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
1954年、東京通信工業(現・ソニー、以下:東通工)でテープレコーダーの製造部長を務める岩間和夫氏が、米国ペンシルベニア州にあるウエスタン・エレクトリック(WE)社を訪れた。
多くの人にとってウエスタン・エレクトリックはまだ聞き慣れない名前かもしれないが、傘下にかの有名なベル研究所を抱えている。世界のチップ産業の土台をなす「トランジスタ」はベル研究所で発明された。1952年、ちょうど米国を視察中だった東通工の創業者・井深大氏は、トランジスタがテープレコーダーの開発に活用できると考え、2万5000ドル(当時のレートで約900万円)でトランジスタの特許使用契約を結んだ。しかしこの決断は社内から猛反対を受ける。トランジスタを発明した米国人でも作れないのに、日本人が製造できるはずはないというのだ。井深氏が買い取った特許権には技術の詳細や製造方法は含まれておらず、どう作るかも分からないものの図面に大枚をはたいたようなものだった。当時、東通工にあった唯一の資料といえば、同じく創業者の盛田昭夫氏が米国から持ち帰った書籍「トランジスタ技術」3冊のみだった。
途方にくれていたとき、前出の岩間氏がトランジスタ研究のため米国に赴くことを申し出る。米国ではウエスタン・エレクトリック社の職員が家族のように喜んで迎えてくれたものの、写真撮影やノートをとることは一切許されなかった。岩間氏は、昼間は研究室でエンジニアをつかまえて質問攻めにし、夜ホテルに戻ってから記憶を頼りに聞いた内容をレポートにまとめ、見たものをスケッチして日本に送った。
岩間氏が4年間にしたためた手書きのレポートは256ページに及び、どのページにも詳細な製造プロセスや説明がびっしり書き込まれている。これが「岩間レポート」だ。このレポートのおかげで、東通工は岩間氏の帰国する1週間前に、見事トランジスタの製造にこぎつけた。
1955年8月、東通工はトランジスタラジオ「TR-55」を発売し、「SONY(ラテン語「Sonus」と「Sonny Boy」が由来)」ブランドで米国市場に進出した。高価ではあったものの、コンパクトで携帯性に優れたTR-55は日本でも米国でも大ヒットとなる。1959年にソニーのラジオは250万ドルを売り上げた。日本半導体の黄金時代が始まったのだ。
国を挙げた支援
1950年代にはトランジスタや集積回路が次々と発明されたが、半導体技術の川下では買い手が慢性的に不足しており、軍需品のビジネスくらいしか成り立たなかった。当時は米軍だけで半導体の売上高全体の35%を占めるほどだったが、トランジスタラジオの登場により、半導体技術に収益性の高い市場が見いだされた。
ソニーのラジオが大ヒットしたことで、川下の巨大な消費市場から収益を上げて技術開発のコストを下げ、さらなる技術の改良に生かすという、半導体企業にとっての成功の道筋が示された。ここでキーワードとなるのが「市場」だ。
ソニーの成功体験で奮い立った日本の半導体産業は、大型コンピューターという大きな市場に着目した。1976年、米国に主導権を握られている半導体メモリDRAM開発で反撃すべく、当時の通産省が呼びかけ、富士通、日立製作所、三菱電機、東芝、NECが参加する「超LSI技術研究組合」が発足する。通産省は政府補助金総額の半分に相当する290億円をこのプロジェクトに投じ、最終的には4000件以上の特許技術の獲得し、京セラ、住友、トッパンフォトマスク、東京エレクトロン、ニコンなどからなるDRAM産業チェーンの構築につながった。
大型コンピューターに使用されるDRAMは、技術的な難度はそれほど高くないものの、需要が大きいため、大規模な生産能力と組み合わせることが必要になる。これは日本人が得意とするところだ。また日本企業はサプライチェーンのあらゆる部分を掌握しているため、その市場シェアを利用してコストの影響を軽減できる。
最盛期には、世界のDRAM市場で8割のシェアを占めるまでになった日本に対し、米国は危機感を募らせるようになる。1981年、フォーチュン誌に「日本半導体の脅威」という記事が掲載された。その挿絵には、1枚のチップの上で日本の相撲取りが弱々しい米国人と向かい合っている様子が描かれている。
圧倒的な優位を築いた日本企業に対し、ついに米国が猛烈な反撃に打って出た。インテルやシリコンバレーの半導体企業が立ち上げた業界団体による粘り強いロビー活動の結果、1985年に「日本の半導体の台頭は米国の安全保障を脅かす」という拒否できない理由で議会に介入を迫ったのだ。
ハードウエアからソフトウエアへ
日本の半導体が衰退した原因は米国の締め付けが原因であり、特に1986年の「日米半導体協定」の影響は甚大だったとの声も大きい。しかし、協定は「5年以内に、日本市場における外国製半導体のシェアを20%以上まで引き上げる」ことを規定したに過ぎない。現在の中国に対する徹底的な輸出規制と比べれば、その威力はタバコの外箱に書かれた「喫煙はあなたの健康を損ないます」という警告文と同じレベルだ。
実際、日本の半導体産業は1990年代は依然として好調な貿易黒字を保っており、衰退し始めたのは2000年代に入ってからのことだ。その原因は米国ではなく、韓国や台湾のチップ産業が台頭してきたことにある。
屋台骨ともいえる産業の衰退は、産業界で繰り返し議論の的になり、常々思い返されてきた。西村吉雄氏は著書「電子立国は、なぜ凋落したか」の中で、日本企業は「製造方法」の研究には長けているが、「何を作るか」の判断がおろそかだったことを指摘している。
西村氏は日本の半導体が1980年代後半に直面した危機を列挙している。中でも重要なのが、「プログラム内蔵方式」の出現により付加価値の源泉がハードウエアからソフトウエアに移ったことだ。インターネットの普及後はますますこの傾向が強まっている。つまりソフトウエアはもはやハードウエアを動かすだけのツールではなくなり、フォトショップやWeChatのようなソフトを開発できれば一気に巨大企業に成長することもできるわけだ。しかし長きにわたって日本人はソフトウエアの持つ付加価値をほとんど意識してこなかった。
「電子立国は、なぜ凋落したか」では日本の半導体産業が衰退した別の理由も示されている。日本半導体の成功は大型の製造設備に支えられたもので、市場は部品から完成品、製造から販売までを自社内で完結させるタテ型の事業形態だった。例えば東芝製の部品を東芝の工場で組み立てて、東芝のOSを搭載し、東芝の販売部門が製品を売り出すという垂直統合の形態だ。
しかしパソコン市場はそうはいかない。サプライチェーンの各部分には川上の部品メーカーから川下の組み立て工場やソフトウエア開発企業など、さまざまな企業が関わっているためだ。ヒューレット・パッカードのパソコンが、インテルやウエスタンデジタルから部品を調達し、組み立てはフォックスコンに委託して、マイクロソフトのOSやAdobeのフォトショップを搭載するという具合だ。
この新たなシステムのもと、付加価値の源泉は製造スキルやコストコントロールから、ソフトウエア開発のアーキテクチャや川下のアプリケーションへと移ってきたが、日本人はこの変化になじめなかった。
1984年、インテルのマイクロプロセッサ8086/8088が出荷台数7500万個という驚異的な数に達し、x86アーキテクチャが確立された。インテルは互換性に重きを置き、どんな開発者でもx86アーキテクチャをベースにしたソフトウエア開発ができるようにした。ソフトウエア開発企業が8086に投じた金額は世界で数十億ドル(数千億円)に上った。
インターネットが普及し始めると個人消費者がIT市場の中心勢力となり、Adobeやグーグル、アマゾン、さらには中国IT御三家「BAT」やポータルサイトなど数多くのソフトウエア企業が誕生した。半導体産業でも新しいビジネス環境が出来上がった。ユーザーがソフトウエアを購入すると、ソフトウエア企業は製品の改良を進める。改良後の製品はシステムリソースが増大するため、チップ企業はチップの性能を高める。ユーザーは最新チップを搭載したハードウエアを購入してソフトウエアを実行する。この一連の流れは「アンディとビルの法則」と呼ばれ、チップの性能向上を促すのは一貫してソフトウエアであることを示している。
残念なことに、経済不況に陥った日本には大手のソフトウエア開発企業もなかった。経済学者の試算によれば、1990年代に米国が情報通信技術(ICT)に投じた金額のGDP比は日本の4倍だったという。しかも日本は英国やドイツ、イタリアよりも低く、G7の中で最下位だった。つまり日本には起業する人も投資する人もいなかったのだ。
西村氏が語ったとおり、日本企業は優れた「ものづくり」の精神にあふれてはいたが、クアルコムやインテルにも、グーグルやアマゾンにもなれなかった。
「技術ではなく、市場で負けた」
「半導体の種類でいえば、日本の成功はDRAM分野に限られている。CPUや携帯電話のベースバンドチップなどは、米国の技術を超えられていない」。東京大学の丸川知雄教授は論文の中で、日本半導体の黄金時代をこうまとめている。
シリコンバレーの発展モデルは、ベンチャーキャピタルの資金に頼って新技術を開発するという、純粋な市場志向だ。効率的ではあるがリソースの統合は難しい。「資金は政府から、技術開発は研究機関で、商業化は企業が担う」という日本型のモデルと比べると、シリコンバレーは制度的に不利である。米国で生まれた技術でありながら、日本人がビジネスとして完成させることが多いのもこのような理由からだ。
しかし1990年代に個人向け電子機器市場が急成長し、「ムーアの法則」通りに半導体の性能が向上し始めると、チップ産業では分業と市場化が進み、大企業の研究機関やベンチャーキャピタルに代表される市場志向の勢力が、新たな技術革新を主導するようになった。最終的に、無数のチップメーカーとソフトウエア企業が激しい競争を繰り広げながら産業チェーンを形成している。
日本人が半導体産業を振り返るときによく耳にするのが、「技術ではなく、市場で負けた」という言い訳だ。トップクラスの演算能力を持つチップを設計するのはもちろん容易なことではない。しかしその先に、チップをもとにソフトウエアを開発する企業や、それにお金を払う消費者がいることを忘れるべきではない。
2022年11月、トヨタやNTTなど日本の主要な企業8社が共同出資して、先端半導体メーカー「Rapidus(ラピダス)」を設立した。日本政府も700億円の補助金を出すなど全面支援を表明している。台湾TSMCに並び立ち、2027年までに2nm半導体の国産化を実現するのが目標だ。これまでの経験を糧として、日本は再び黄金時代を築けるだろうか。
作者:WeChat公式アカウント「遠川研究所(ID:caijingyanjiu)」、李墨天
(翻訳・畠中裕子)
原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録



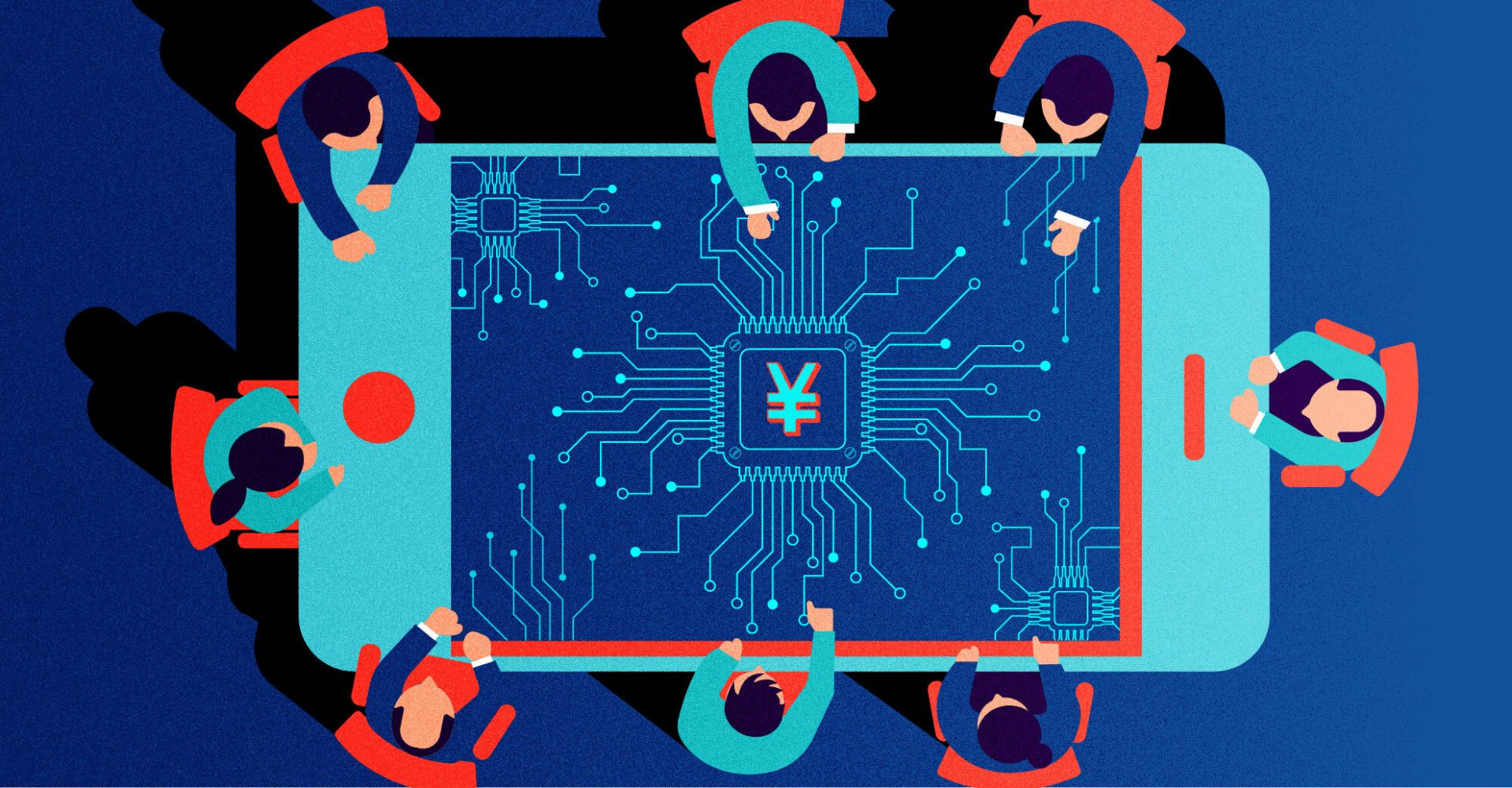


山東省の浄水工場、業界初の「ライトハウス」認定XxjjpbJ000056_20260129_CBPFN0A001519-scaled.jpg)
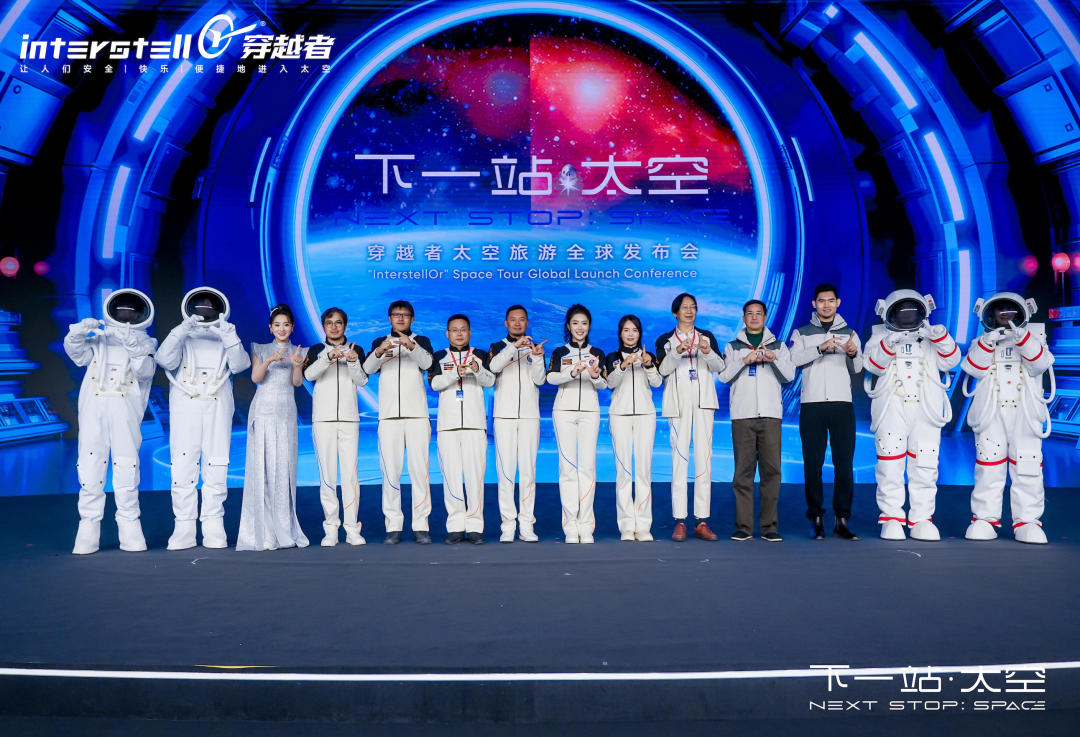



 フォローする
フォローする フォローする
フォローする




山東省の浄水工場、業界初の「ライトハウス」認定XxjjpbJ000056_20260129_CBPFN0A001519-510x369.jpg)