セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
中国の電気自動車(EV)輸出が世界市場を席巻し、存在感が急速に高まるなか、2026年1月1日からEVの輸出管理ルールが大きく変わる。中国政府は今後、純電動乗用車(BEV)を輸出する企業に対し、より厳格な「輸出許可管理」を適用すると発表した。
日本でも中国製EVの輸入は急増しており、今年1〜8月だけで約1万3000台が日本に流入。BYD(比亜迪)やテスラ(上海工場製)はもちろん、ミニバンや小型商用車、軽EVまで幅広い車種が含まれる。
では、今回拡大される「輸出許可管理」とはどんな制度で、何が変わるのか。さらに、大阪・関西万博でも注目を集める中国製EVバスの輸入実態や、認証制度との関係にも踏み込みながら、中国のEV輸出管理の全体像を整理する。
中国の「輸出許可管理」とはどんな制度?
中国の「輸出許可管理」とは、政府が重要物資・安全保障関連品目・資源などの輸出をコントロールするために、企業に輸出許可を義務付ける制度である。輸出企業は、品目リストや政策変更を常に確認し、必要な許可を取得した上で通関する必要がある。指定された品目を中国から輸出する際に政府の許可(輸出ライセンス)を取得しなければならない制度で「中華人民共和国対外貿易法」および「中華人民共和国貨物輸出入管理条例」に基づき制定されている。
中国商務部は税関総署と共同で、毎年「輸出許可管理対象貨物目録」を策定・調整・公表しており、商務部は毎年「輸出許可管理対象貨物分類別目録」を策定・調整・公表している。
最新の輸出許可管理の対象となる貨物一覧はこちら(ページの一番下にあるPDF)で確認することが可能だ。
2026年1月1日から対象となる「EV乗用車」とは?
2026年1月1日から輸出許可管理が厳格化される。中国商務部など4部門は9月26日、純電気自動車(BEV)の輸出に関し、2026年1月1日から輸出許可管理を実施すると発表した。対象となるのは、「駆動用電動機のみを搭載し、車両識別コード(VINコード)を有する乗用車」(参考となる中国のHSコード8703801090)とされている。
その根拠となる通達は「公布対純電動乗用車実施出口許可証管理 (商務部 工業和信息化部 海関総署 市场監管総局公告2025年第54号)」だ。
「貨物名称が『駆動用電動機のみを搭載した車両識別コード(VINコード)を有するその他の乗用車』(税関商品番号8703801090参照)であるものに対し、輸出許可証管理を実施する」と規定している。
具体的には税関商品番号8703801090の+3桁CIQコード(中国税関申告13桁税関コード)、GB/T 3730.1-2022「汽車、挂車及汽車列車的術語和定義 第1部分:類型」をもとにすると以下に細分類される。
しかし、実際には、これらの車種のほとんどはすでに輸出許可が実施されている。中国で製造されたBEV乗用車や小型商用車を輸入販売している企業に確認したところ、ミニバンから軽トラックまですべて輸出許可管理は取得しているとのこと。そのため、今回の対象追加は品質管理を目的とした「並行輸入車」への対応が中心になるのではないかという見方もある。
中国から世界に輸出されるBEV乗用車(HSコード87038010〔駆動用電動機のみを搭載し車両識別コード(VINコード)を有するその他の乗用車〕について、ジェトロがグローバル・トレード・アトラスのデータを基に集計したところ、2025年1~8月に中国から世界へ向けた輸出額の合計は222億3140万ドル(約3兆5000億円)、輸出台数は108万台だった。この期間、最大の輸出先はベルギーで金額は32億2253万ドル(約5060億円)、輸出されたBEV乗用車の台数は14万1248台。
同じく日本向けは3億5330万ドル(約555億1400万円)、1万3262台という統計が出ている。
日本向けの台数が8カ月で約1万3000台超とはかなり多いという印象だ。「日本向け」の中に含まれるのは中国国内で製造されるBYD乗用車はもちろん、中国・上海工場で製造されたテスラモデル3やモデルYなどもある。ちなみに、日本で販売されるテスラ車の大半は上海工場で製造されている。
また、日本でいうところのセダンやクーペ、SUVなどの「乗用車」だけではなく、乗車定員9名までのミニバン(先日日本導入を発表したZeekr009など)や日本では貨物車扱いになる「バン」なども含まれる。
さらに、軽のワンボックス(柳州五菱製ASF)や軽トラック(同)、HWエレクトロ「ELEMO」シリーズ等も対象となる。先日開催されたジャパンモビリティショーに、新開発の軽トラックや軽ワンボックスを出展したASFに確認したところ、「輸出許可は申請の上、許可を取得して日本に輸出されている」という回答だった。
中国EVミニバン「ZEEKR 009」が日本上陸、社長車や富裕層インバウンドに照準 フォロフライ1300万円から輸入で提供
ジェトロによれば、この統計には「再輸出」車両も中に入っているという。再輸出とは、中国から日本に輸入されたEVが、日本から海外へ再び輸出されるケースを指す。
では、なぜ今、BEV乗用車の輸出許可管理の範囲を拡大するのか?
中国政府の発表文書では、自動車輸出秩序の正常化、新エネルギー車貿易の健全な発展を促進し、国家安全保障の確保や重要資源の保護などが目的として挙げられる。また、中国は世界最大のBEV生産販売国であり、その“誇り”や責任も背景にあるとみられる。すなわち、「BEVを売りっぱなしで、アフターサービスなどを行わない並行輸入業者を排除したい」という思いも大きいだろう。
輸出には「CCC認証」が必須だが、EVモーターズ·ジャパンのバスは受けているのか?
今回の措置の根拠となる通達では、「輸出資格を申請する企業の条件、管理方法、申請手続き、輸出許可証の申請と交付等については、商務部、工業情報化部、税関総署、旧国家品質監督検査検疫総局、旧国家認証認可監督管理委員会が共同で発出した「自動車及びオートバイ製品の輸出秩序の一層の規範化に関する通知」(商産発〔2012〕318号)の関連規定に基づき実施する。」と規定している。
商産発〔2012〕318号には以下の通り規定されている。
「一、輸出資格を申請する生産企業が備えるべき条件」
(一)自動車・オートバイ生産企業は、工業情報化省の「車両生産企業及び製品公告」に掲載されていること。有効な国家強制製品認証(CCC認証)を有すること。
CCC(国家強制性製品認証)は、企業に対してではなく製品(車両)毎に付与されるもので輸出許可申請の対象はCCC認証済みであることが前提となる。また、電気商用車の安全部品(バッテリー、モーター、充電システムなど)は部品単位でもCCC認証が必須で、未認証品の輸出は禁止され、税関で検査される。これらの安全部品についてはすでに中国国内で販売されているため、基本的にはCCC認証は取得済みと見られる。

また「純電気バス(BEVバス)は、輸出許可管理の対象ではない!」と考える人もいるかもしれないが、それは誤解である。ジェトロに確認したところ2017年1月1日より、以下のBEVバスが輸出許可管理の対象になっている。
最初の数字はHSコード(国際貿易の商品名称と分類を世界的に統一するための6桁のコード番号)
8702401000 (座席数30以上の大型BEVバス)
8702402010 (座席数20-23のBEVバス)
8702402090 (座席数24-29のBEVバス)
8702403000 (座席数10-19のBEVバス)
※「バス」(客車)のカテゴリーに入る10~30座以上のバスはすべてが輸出許可管理の対象になっている。
輸出許可管理は非常に厳しく、無許可で輸出した場合は商品の没収や罰金に加えて、企業の輸出資格の停止・取消が行われることがある。さらに、CCC認証の書類を偽造して輸出許可を得るなど重大な違反の場合は刑事責任までが課せられる。
さて、ここで気になるのは、以前、当メディアで記事を公開した「EVモーターズ・ジャパン」の中国製電気バスだ。EVMJが中国から輸入するバスは、威馳騰汽車(WISDOM)、愛中和汽車、南京恒天嶺鋭汽車の3社で製造されているが、いずれも中国国内での販売するための電気バス製造の許可は出ておらず、「輸出専用」として当局からEVバス製造の許可が出ている。
CCCは本来、中国国内での使用に関する安全基準であるため、日本から中国に輸出する車両などももちろんCCC認証を得ている。一方、EVMJ3社のバスが中国国内では使用できないためCCC認証を取得していない可能性が高い。
バスに使われている窓ガラスにはEマーク(R43の窓ガラス規格に合格)とCCCマークが入っている。これは基準に合格したガラスメーカーが製造時に組み入れているものなので、車両全体のCCCマークとは異なる。

EVMJのバスは3社が車両全体のCCC認証を取得しているかどうか?日本国内のバス事業者、EVMJ関係者、中国バスメーカーなど複数筋に確認した。しかし、得られた証言は一貫しており、CCC認証は取得してない可能性が高い。もちろん、フロントガラスなどにもCCCのステッカーは貼られていない。
では、CCC非取得とみられる車両が、どのように中国当局の輸出許可を得て日本へ輸出されたのか——ここに最大の疑問が残る。現在、関係機関の協力を得て真相を突き止めるべく取材を進めている。もし、本記事を読まれた方の中に、EVMJバスの輸出許可管理やCCC認証取得の有無について具体的な情報をお持ちの方がいれば、ぜひエビデンスとともに編集部または筆者([email protected])まで情報を寄せていただきたい。
(文:自動車生活ジャーナリスト 加藤久美子)
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録







「墓参り」で推し活 歴史人物に熱中する中国の若者XxjjpbJ000164_20251223_CBPFN0A001442-scaled.jpg)



 フォローする
フォローする フォローする
フォローする

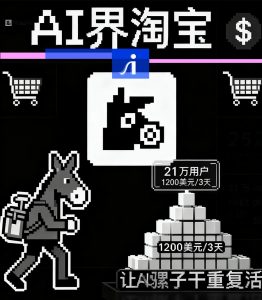


「墓参り」で推し活 歴史人物に熱中する中国の若者XxjjpbJ000164_20251223_CBPFN0A001442-510x369.jpg)



「中国の靴の都」福建省晋江市、スマート製造で進化中XxjjpbJ000153_20251224_CBPFN0A001508-510x369.jpg)


