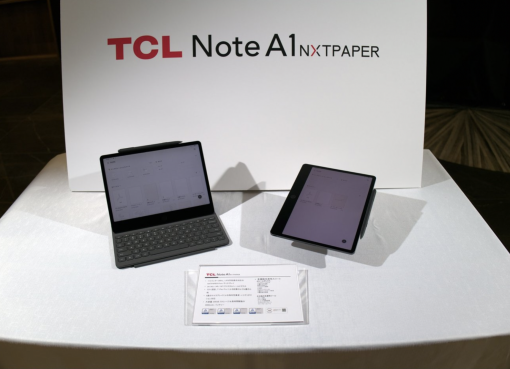36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
2025大阪・関西万博の中国パビリオンでは、5月12日~14日に「深圳ウィーク」が開かれ、これに併せて「深圳—大阪イノベーション・コラボレーション大会(関西地区中日企業経済交流大会)」も大阪市内のホテルで開かれた。
深圳と日本企業のオープンイノベーションを促進するのが狙いで、IT大手の騰訊控股(テンセント)や電気自動車(EV)大手の比亜迪(BYD)、スマートフォン大手のHonor(栄耀)など深圳を代表する大手企業のほか、日本からも伊藤忠商事や、パナソニックホールディングスも登壇し、日中ビジネスの促進や企業連携の可能性について話した。
深圳は「中国のシリコンバレー」とも呼ばれる。外資への市場開放と、民間企業の育成を進めた「改革開放」路線で「経済特区」に指定され、1980年代以降に小さな漁村からイノベーションの中心地に大きく変貌を遂げた。あらゆる電子機器の製造業が集積し、「世界の工場」と呼ばれる中国の製造力を支えてきたほか、華為技術(ファーウェイ)やBYDといった世界的な企業もこの地から生まれている。中国の省で最大の経済規模と日本とほぼ同じ人口の広東省に位置し、国際金融センターの香港に隣接しており、優れた人材と投資資金を活用したスタートアップを育成する強固なエコシステムを持つのが強みだ。

今回のイベントには、深圳を拠点とする30社超のスタートアップが出展した。中でも来場者の関心を集めたのが、ロボット関連の企業だ。日本でも話題の人型ロボットの「UBTEC(優必選)」や、ネコ型配膳ロボット「BellaBot(ベラボット)」で知られるサービスロボット大手「Pudu Robotic(普渡科技)」に加え、新興の有力企業も多数出展した。以下では、その中からいくつかの企業を紹介する。
プロの味を再現する調理ロボット「T-Chef」
調理ロボットを開発するスタートアップ「T-Chef(智谷天厨)」は、日本市場の開拓を本格化させている。
同社のロボットは、必要な食材をセットするだけで、AIが食材の混合や火力調整などを自動で制御し、約2分間でプロ級の料理を完成させる。中華を中心に韓国やタイ、イタリアンなど世界各国の料理、2000以上のメニューに対応しており、企業のニーズに合わせて追加のカスタマイズもできる。

T-Chefは2023年から海外進出を進めており、すでに香港やシンガポール、韓国、アメリカ、ドバイなどで事業を展開している。2025年からは日本を重点市場と位置づけ、本格参入を開始した。人手不足や人件費の高騰に悩む日本の飲食業界に向けて「味の均一化」「省人化」などのメリットを訴求する。
海外事業の責任者である厳紹鴻氏は「日本の飲食業界では、料理人の不足と人件費の上昇が深刻な課題となっている。ロボットによる自動化は、労働力不足の解消だけでなく、作業効率の向上で料理の提供の遅れを防ぐことができるなどサービスの向上にもつながる」と語った。一人の料理人が3〜4台のロボットを操作して、繁忙時間帯でも複数のメニューを短時間で提供できると説明した。
調理ロボットはレシピ通りの温度や分量、調理時間を正確に再現できるため、誰が操作しても仕上がりが一定の水準に保たれ、チェーン店などで「味のばらつき」を防ぐための有力な選択肢となる。すでに東京にある四川料理チェーン「麻辣大学」に導入済みで、日本の代理店パートナーとの協業を強化し、年内に100台規模の導入を目指す。日本法人の設立も視野に入れている。

日本で中華料理は食文化の一つとして定着しており、日本人の口に合わせた料理を提供する中華料理店も多い。一方で、近年は中国の本場に近い味付けの中華料理を提供する「ガチ中華」と呼ばれる飲食店も増えており、日本の中華料理店の市場は今後も堅調に推移するとT-Chefはみている。
日本の飲食店への導入をさらに促進するため、同社は日本人の料理人の協力を得て、和食メニューの開発にも取り組んでいる。現在、生姜焼きやカレーライス、きんぴらごぼう、肉じゃが、五目チャーハンなど、20種類以上のメニューを作ることができる。年内に80種類にまで拡大する予定だ。
調理ロボットは、単に料理を提供するだけの存在ではないという。T-Chefのスマートキッチンソリューションは、スマート機器とデジタルシステムを中核に据えており、ソフトウェア面ではクラウドキッチン用アプリ、食品安全管理プラットフォーム、メニュー開発システムを統合している。これにより、機器の遠隔操作や食材のトレーサビリティ(安全追跡)が可能となり、ビッグデータに基づくレシピの最適化も実現できる。厳氏は、最終的にはこうしたデジタル技術を活用し、「スマートキッチン」の構築を目指していくと語る。

除草から収穫まで──次世代農業ロボット「COONEO」
農業分野からは「COONEO(酷牛)」がスマート農業ロボットを出展した。農業・食品分野で世界トップクラスとされるオランダ・ワーゲニンゲン大学出身の蒋奇軍博士によって設立された。
すでに多機能型のスマート農業ロボットをリリースしており、なかでも主力の「RoboOX mini」は、耕耘や種まき、収穫、運搬といった作業を網羅するオールインワンのロボットとして注目を集めている。
自律走行機能を備え、運転席がない設計とすることで、そのスペースに多様な作業ができるモジュールを組み込める点が特徴だ。正確な種まきや、除草、剪定、収穫などを一台でこなすことができる。

車体が小さいため、日本の中山間地などでも農作業に活用できる。キャタピラのような回転するベルトで動く農業ロボットも開発しており、より幅広い用途に活用できるようにする計画だ。
蒋博士は「当社のロボットアームは高感度のセンサーを搭載しており、雑草を一本ずつ抜くことができる。農薬使わずに食の安全を求める日本の市場ニーズにも応えられる」と語る。
蒋博士がマンゴー農園で作業するロボットアームの動画を流して説明した。まず、ロボットはマーシンビジョンを用いてマンゴーの熟成度合いを判断し、収穫する。ロボットアームは精密な動作が可能で、果物を傷つけずに収穫できるという。また、果物を積んだカートがいっぱいになると、カートは自動で交換されるよう設計されている。

日本では農業従事者の高齢化と人手不足が深刻化しており、蒋博士は「日本の農業はすでに機械化が進んでいるが、まだ農業機械のスマート化や小型化の余地は残っている」と指摘した。現在、JETRO(日本貿易振興機構)や大手商社との連携も進めており、今後は農業関連の展示会などを通じ、日本市場での展開を加速させる方針だ。
下では、深圳発のマッサージロボットや清掃ロボットのスタートアップを紹介していく。
(取材・編集:36Kr Japan編集部)
36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録













 フォローする
フォローする フォローする
フォローする