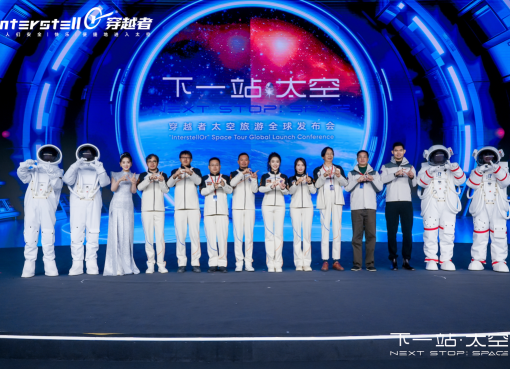セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
2025年6月、中国で高い人気を博している広汽トヨタ(広州汽車との合弁)「bZ3X」と、東風日産(東風汽車との合弁)「N7」が、それぞれ6030台、6189台を販売し、合弁系EV販売台数ランキングでトップ2を獲得した。
これまで日本車は、中国特有の電気自動車(EV)需要を的確に捉えきれず、現地勢にシェアを奪われてきた。しかし、2023年以降に活発化した「合弁相手との共同開発」の取り組みが年々成熟し、ようやく実を結んだと言える。
bZ3Xは2025年3月の発売と同時に予約受付を開始し、1時間で1万件の受注を獲得。一時は予約サイトへのアクセスが困難になるほど反響を呼んだ。そんなトヨタが次に中国市場へ投入するのが、広汽トヨタとは別の合弁会社である一汽トヨタが製造・販売を担当する「bZ5」だ。
このbZ5は、bZ3Xと同じく「上海モーターショー2023」でコンセプトモデル、「北京モーターショー2024」で量産モデルがお披露目された。当初は「bZ3C」という車名が与えられていたが、発売直前に開催された「上海モーターショー2025」で「bZ5」へと改名され、予約受付を開始した経緯を持つ。
そこで筆者は、中国市場専売モデルであるこの「bZ5」に試乗してみた。
老舗メーカーの底力:bZ5が示した“安心感ある走り”
典型的なSUVボディでファミリー層をターゲットにするbZ3Xに対し、bZ5では全高を抑え、ワイドで伸びやかなフォルムが特徴的だ。内外装色にはどちらも鮮やかでビビッドな色を用意し、ターゲットは主に中国の若年層としている。
ボディサイズは全長4780 mm x 全幅1866 mm x 全高1510 mm、ホイールベース2880 mmと、日本基準で考えると少し大きめだが、中国市場では標準的なサイズ感だ。フロントデザインはトヨタが2021年ごろから採用している「ハンマーヘッド」が先進的な印象を感じさせる。一方でサイドのキャラクターラインは2023年に発売した電動セダン「bZ3」の流れを汲みながらも、より曲線的で洗練されたデザインに仕上がっている。


bZ5はトヨタ車でありながら、開発は一汽トヨタに加えて、EV最大手のBYDも参画している。トヨタは2020年、BYDとEVの研究開発に注力した合弁会社「BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY(BTET)」を設立しており、その最初の成果が先述の「bZ3」だ。
bZ3ではBYD傘下のパワートレインメーカー「弗迪動力(フィンドリームズ)」製の駆動用モーターと駆動用バッテリーを採用し、車体プラットフォームはトヨタ独自の「e-TNGA」とBYDの「e-Platform 3.0」を融合させた設計となる。bZ5のプラットフォームに関する詳細はまだ明かされていないものの、bZ3同様に駆動用モーターも駆動用バッテリーも、どちらもBYD製だ。
駆動方式は前輪駆動のみで、出力は268 hp、トルクは330 Nm。四輪駆動モデルは設定されていない。昨今の中国製EVはツインモーター構成で出力400~500 hpという高性能モデルも多いが、都市部での通常の走行において、これほどのパワーは過剰だ。bZ5のスペックでも加速性能に不足はなく、むしろ運転に不慣れなユーザーにとっては、ちょうど良い扱いやすさと言える。
また、中国の都心部では路地裏や細い通りでの路駐が多いので、大型車は運転しづらい印象を持たれがちだが、bZ5にはルーフにLiDARユニットが搭載されており、周囲との距離を高精度に測定してドライバーに知らせてくれるため、狭い場所でも安心して走れる。このLiDARユニットは、中国の自動運転ベンチャー「Momenta(モメンタ)」と共同で開発したレベル2+相当の運転支援機能を支える重要なハードウェアのひとつだ。市街地や高速道路でのハンズオン自動運転(NOA:Navigation on Autopilot)や、車外からのリモート駐車操作、分岐・合流時の自動レーンチェンジなど、高度な支援機能を搭載している。
乗り心地については、中国の新興メーカーが手がける未熟なEVと比べたら格段に優れており、「さすがは老舗メーカー」と感じさせる仕上がりとなっている。フロントはマクファーソン式ストラット、リアにマルチリンクという組み合わせなのだが、実はリアがトーションビームのbZ3Xよりも豪華な仕様だ。一方で後輪が段差を踏み越える際の振動音がキャビン内に結構響くのはやや気になるところ。これは5ドアハッチバックである以上、ある程度は避けられない問題でもある。試乗した車両がまだ新しく、サスペンションなどの足回りが馴染んでいない可能性も考えられる。

搭載するバッテリーは容量65.28 kWhと73.98 kWhの2種類を用意され、中国独自のCLTCモードで計測した一充電航続距離はそれぞれ550 kmおよび630 kmと公表されている。bZ5のグレードはこの2種類のバッテリーを基軸に、装備や運転支援機能が異なる「JOY」「PRO」「MAX」を設定する合計6グレードから選べる。価格帯は12.98~19.98万元(約270〜410万円)とbZ3Xよりも2〜4万元(約40~80万円)ほど高い水準となっている。
「現地主導」開発が奏功
bZ3Xが中国市場でヒットした最大の要因は、その「コストパフォーマンス」にある。例えば、中国市場向けに初めて設計した「bZ3」は当初、メーカー希望小売価格16.98〜19.98万元(約350〜410万円)で発売された。だが、同車格でよりエンタメ機能や運転支援機能が充実する中国EVが多数存在しており、早くもその価格が原因で競争力を落としてしまった経緯を持つ。
筆者も実際にbZ3を試乗し、車両の質感や基本性能の高さは十分に感じられたが、一方で「普通すぎるEV」という印象も否めず、先進性や個性を重視する中国の消費者には物足りなかったはずだ。現在は各グレードで4万元ほど値引きされており、月間販売台数は3000台前後を維持している。
また、bZ3以前に中国で販売された「C-HR」や「イゾア EV」などはガソリン車を電動化したモデルで、「エンジン車からの転用(油改電)」と揶揄されることも多かった。こうした背景もあり、トヨタが専用設計のBEVに本格的に舵をきったことは、中国市場での競争力強化に向けた重要な転換点となった。
こうした反省を踏まえ、bZ3Xでは広汽トヨタが開発の主体となり、中国の消費者が好む要素をふんだんに盛り込んだ。Momentaと共同開発した運転支援機能や、物理ボタンを極力排除した未来的なコックピット、そしてエンターテインメントを強化したインフォテインメント機能など、bZ3よりも大幅に進化した点だ。

この内容を10.98~15.98万元(約230~330万円)で発売したのだから、トヨタとしてもかなりの攻めの姿勢を見せたことになる。結果的にbZ3Xは、中国市場で大ヒットを記録するに至っており、「現地主導の開発」が功を奏した好例となっている。
bZ3Xは卓越したコスパによって市場で高い評価をえているが、bZ5が同様の人気を獲得するかはまだ判断が難しい。ただし、発売初月は約1500台を販売しており、今後の成長が期待できる滑り出しとなった。
さらに、2026年に広汽トヨタから全長5メートル級の電動セダン「bZ7」を投入する計画だ。同モデルでは、トヨタ車として初めてファーウェイ製のコックピットシステムを搭載する見込みで、インテリアも木目調パネルやマットシルバーの装飾が採用され、高級感あふれる室内空間を演出している。
現地ニーズに応える柔軟戦略
これまで発売したbZ3XやbZ5、発売予定のbZ7、そして未発表の中国向け次期カローラでは中国人エンジニアが開発を主導する「RCE(Regional Chief Engineer)」制度を取り入れており、現地の需要へ的確に、素早く応えられる開発体制となる。
また、中国市場でEVと並んで注目されている「レンジエクステンダー付きEV(EREV)」に関しても、トヨタは大型ミニバン「シエナ」と大型SUV「ハイランダー」の次期モデルで投入するとも明かしている。トヨタがEREVを発売するのは初の試みであり、中国市場の特色ある需要に応えようという意思の現れだろう。
こうした多様化する中国市場のニーズに柔軟に応えるには、外資系メーカーにとって相応の体力と適応力が求められる。これは日本メーカーだけでなく、欧州勢にも同じことが言える。例えば、ドイツのフォルクスワーゲン・グループでもフォルクスワーゲンやアウディといったブランドで中国の合弁相手とのEV共同開発を加速させている。今後もこういった「共同開発EV」を目にする機会は増えていくことだろうし、自動車開発は新たなフェーズへと移行しているとも感じさせる。
(文:中国車研究家 加藤ヒロト)
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録






AI予測システムで洋上風力発電をスマート管理 江蘇省XxjjpbJ000093_20260129_CBPFN0A001905-scaled.jpg)




 フォローする
フォローする フォローする
フォローする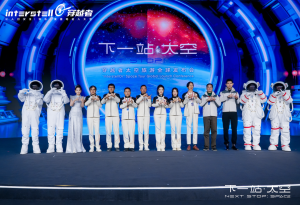

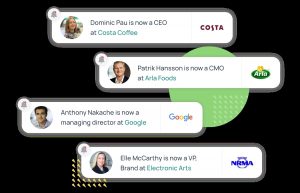
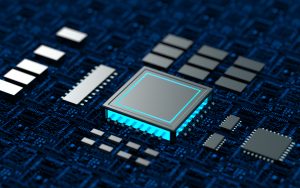

AI予測システムで洋上風力発電をスマート管理 江蘇省XxjjpbJ000093_20260129_CBPFN0A001905-510x369.jpg)



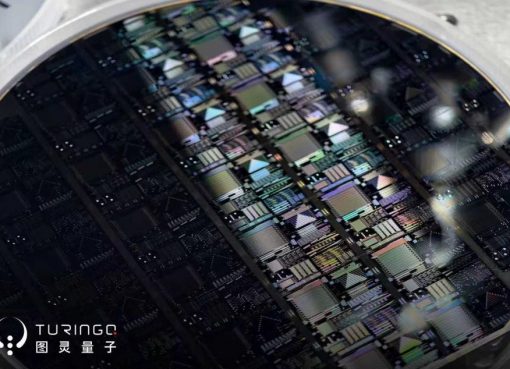
山東省の浄水工場、業界初の「ライトハウス」認定XxjjpbJ000056_20260129_CBPFN0A001519-510x369.jpg)