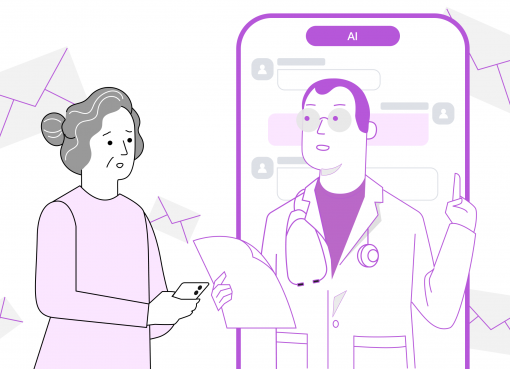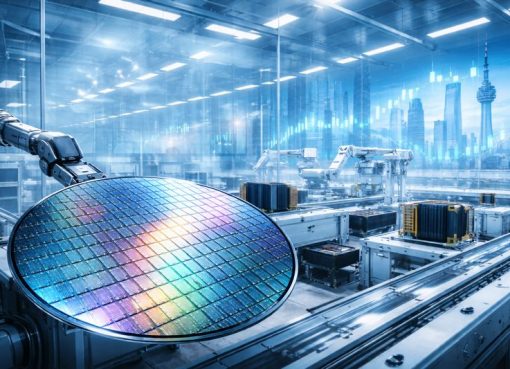原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)が独自開発した運転支援システム(ADAS)の最新版「乾崑ADS 4.0」の本格導入に向けて期待が膨らむなか、同社のスマートカーソリューション・ビジネスユニット(BU)の靳玉志CEOから、これまでの実績が公表された。
今年7月時点で乾崑ADSを搭載した車両は100万台に達し、走行距離は累計40億キロとなった。また、ファーウェイ製LiDARの出荷台数も100万台を突破した。
8月末までに、ファーウェイと提携する自動車ブランドから計28車種が発売された。ファーウェイ主導のEV連合による問界(AITO)、享界(STELATO)、尊界(MAEXTRO)、智界(LUXEED)、尚界(SHANGJIE)のほか、BYD傘下の「方程豹」や「阿維塔(AVATR)」、「嵐図(VOYAH)」、さらにアウディなども含まれている。
靳CEOは、この実績が同社の長期戦略に基づく取り組みの結果であると強調する。ファーウェイは、2014年から実に10年にわたってスマートカーソリューション事業に投資を続け、24年にようやく黒字化を達成した。しかし具体的な商業化目標を設定してはおらず、あくまで技術主導型の長期的な成長を目指している。
自動運転分野の異なるアプローチ:VLAとWA
自動運転を実現するための技術的アプローチに関して、ファーウェイは業界の主流とは異なる立場をとっている。多くの自動車メーカーが採用している「VLA(Vision-Language-Action)モデル」は、映像を「言語トークン」に変換して学習させ、大規模言語モデル(LLM)を用いて制御命令を生成する。成熟したLLMの強みを生かしたこの方法は、一見すると近道のように思えるが、靳CEOは完全自動運転を実現する“究極”のアプローチではないとの考えを明らかにしている。
ファーウェイが選んだのは、より難易度の高い「WA(World-Action)モデル」だ。これは視覚などのマルチモーダルな感知データをそのまま車両制御に利用する仕組みであり、データを言語に変換するプロセスを省くことで、より人間の直感に近い意思決定と制御が可能になる。ファーウェイはWAモデルをベースにした「WEWA(World Engine+World Action)モデル」を打ち出し、乾崑ADS 4.0に導入すると発表した。
コストと長期的価値

車両のライフサイクルには、運転支援システムの継続的なアップデートやメンテナンスが欠かせず、それにはコストが伴う。運転支援機能の無料提供をうたう自動車メーカーもあるが、期間限定であったり、車両価格にコストを織り込んでいたり、一部機能のみを提供したりしている。それに対してファーウェイは、乾崑ADSの継続的なアップデートを保証しており、初期費用は高めであっても、長く使うほど利用体験は向上し、長期的にはむしろコストが抑えられる。
このライフサイクル全体を通じて車両を管理するという考え方は、ファーウェイのスマートコックピット「鴻蒙座艙(Harmony Space)」にも取り入れられている。
鴻蒙座艙はMoLA(Mixture of Large Model Agent)アーキテクチャをベースに、さまざまな機能に特化したモデルを横断的に連携させ、アプリケーション・ハードウエア・デバイスを統合する仕組みを備えている。一部の自動車メーカーがコスト削減のためにソフトとハードを切り離す動きを加速しているのに対し、ファーウェイはソフトとハードを高度に結び合わせたフルスタックモデルを貫き、優れたユーザー体験やアップデートの利便性に重点を置いている。
今後の取り組みについても明確なビジョンを描いている。2026年に高速道路での自動運転レベル3を実現するとともに、都市部でレベル4の試験運用を開始する。27年には自動運転による幹線輸送の試験運用と、都市部でレベル4の大規模商用化を実現。28年には自動運転による幹線輸送の大規模商用化を目指す。さらに、スマートコックピットを「デジタルアシスタント」へ、AIを「AIエージェント」へと進化させ、より主体的で個々に合わせたサービスを提供できるよう努力を傾けていくという。
(翻訳・畠中裕子)
原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録









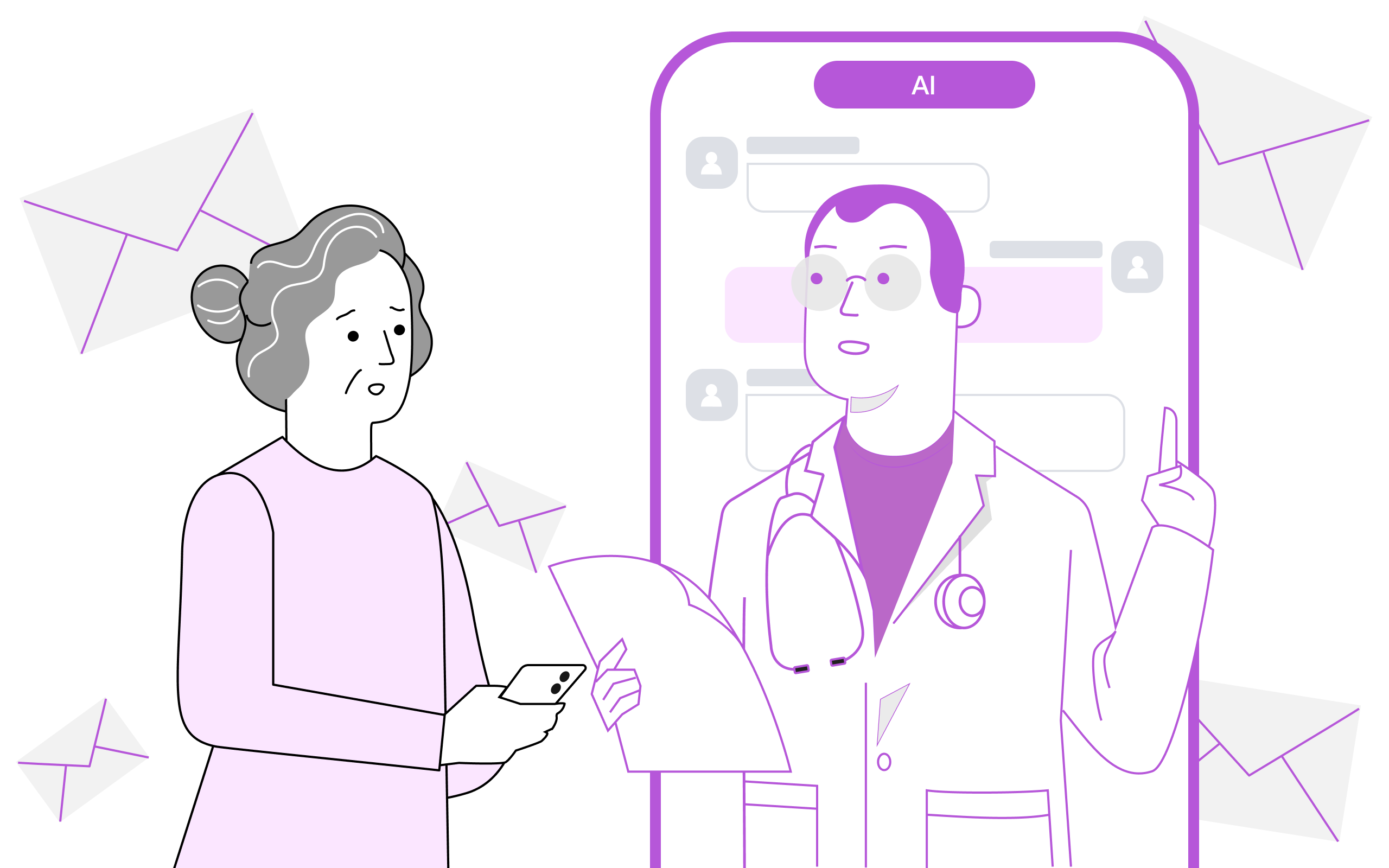

 フォローする
フォローする フォローする
フォローする