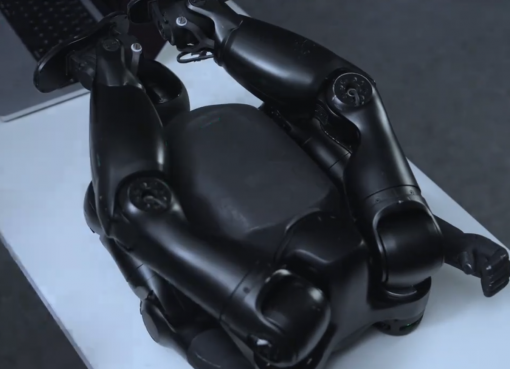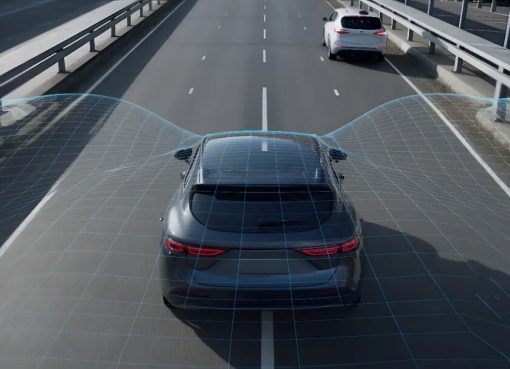セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
中国の一部の若者の間で、レンタルのカメラ、衣類、おもちゃなど、デジタル製品からアウトドア用品、家や自動車からマタニティー・ベビー用品まで、「なんでもレンタル」するブームが起きている。
国家市場監督管理総局発展研究センターが電子商取引(EC)大手アリババ・グループ傘下の金融会社、螞蟻集団(アントグループ)と作成した「循環経済を背景とする消費レンタル産業の健全な発展に関する白書」によると、中国のレンタル経済の2024年の取引額は4兆2000億元(約88兆円)を超え、前年比32%増加し、利用者は7億5000万人を上回った。
中国の調査会社、易観分析(アナリシス)は報告書「中国新レンタル産業洞察2025」で、既存のレンタル産業は家、自動車など、価値の非常に高い商品が中心だったが、現在は対象商品が充実し、レンタル方法が柔軟になり、レンタル期間も多様化し、消費者を強く引き付けているとした。
生活関連サービス大手、美団のプラットフォームデータから、レンタル需要の多角化傾向が明らかとなった。今年8月の検索件数は、「カメラ」が前年同月比63%増、「ウェディングドレス・フォーマルウエア」が2.1倍、「ドローン」が89%増、「ベビーカー」が2.7倍となり、さまざまな消費シーンに広がっている。
重慶工商大学経済学院の熊興副教授によると、レンタル経済はこれまでの家、自動車から、衣類、化粧品、デジタル製品、マタニティー・ベビー用品、オフィス用品へと分野を広げ、「品目の多角化、サービスのデジタル化、需要の高品質化」の特徴が際立った。
「レンタル」は多くの若者にとって、新たな価値観となっている。彼らは「持つ」ことを手放して「使う」ことに転向し、より柔軟で気軽なライフスタイルを楽しんでいる。
南京市の王琳さんは毎月、衣類レンタルサービスサイトを利用し、デザインやブランドの異なる衣類を10数点、300元(約6300円)未満でレンタルしている。クローゼットのシェアは多くの若者の生活に溶け込み、漢服(漢民族の衣装)や旗袍(チーパオ、チャイナドレス)などの中国の伝統衣装も人気を集めている。
レンタルサービスサイト「芝麻租賃」では、1~6月の取引額が前年同期比71.6%増加し、利用者のうち30歳以下が6割以上を占め、「00後」(2000年代生まれ)のレンタル件数は3倍に増えた。
「90後」(1990年代生まれ)と「00後」は、レンタル消費の主力となりつつある。彼らの価値観は「持つよりも体験」を重視しており、需要をすぐに満たすと同時に新鮮さを追い求め、コストパフォーマンスとエコも配慮している。広東省の曁南大学経済・社会研究院の劉詩濛教授は、物質的・文化的生活水準の向上に伴い、若い世代の消費需要が単一から多様化や個別化へと移行していると指摘。旅行用品、アウトドア用品、ぜいたく品など、使用頻度が低い、またはハードルの高い商品を体験してみたい人が増えており、レンタルはこの流れにマッチしているとした。【新華社北京】
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録













 フォローする
フォローする フォローする
フォローする