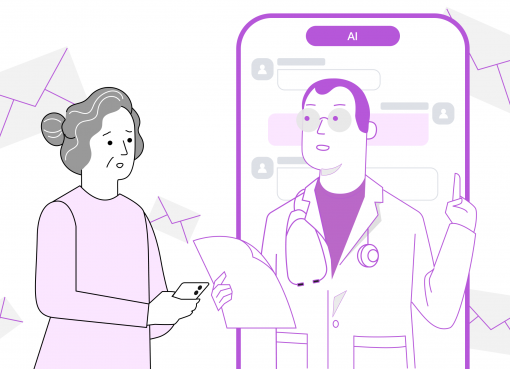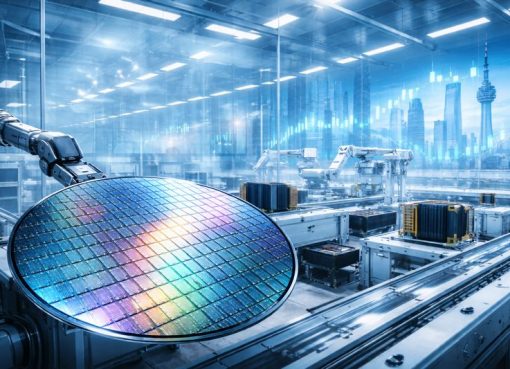36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
高市早苗氏が自民党の総裁に就任したことで、同氏を支持する小野田紀美参院議員の中国製掃除ロボットに関する過去の発言がSNSであらためて話題になっている。
議員会館に掃除ロボットが導入されたことは、2024年以降複数の議員が報告していた。自民党の上月良祐参院議員は2024年5月、ロボットが自走する動画をブログに掲載し、「よく見るとロボットがひとり(一台)でお掃除してくれてました。なんとも可愛くて、頑張ってねと心の中で声をかけました」と記している。
鈴木貴子衆院議員は同9月、「朝から #茂木敏充 選対として、重ねてのご支援のお願いに@SakonYamamoto(筆者注:山本左近氏)と会館をまわっていたら!お掃除ロボットに遭遇」と絵文字付きでX(旧ツイッター)に投稿。立憲民主党の神谷裕衆院議員も同月、Xに「一生懸命なお掃除に感謝です。びっくりしてロボット追いかけていたら、偶然トイレから戻って来た枝野さんに見られてしまいました」と記した。
与野党の壁を超えて議員たちが掃除ロボットに興味津々な様子がうかがえる。だが小野田議員だけは、けなげに掃除するロボットにほっこりすることなく、厳しい目を向けた。
小野田議員は今年4月9日の参院地方創生・デジタル特別委員会で、議員会館の掃除ロボットについて「あれ、どこの会社かご存知ですか。追っかけ回して写真を撮って後で調べたら中国企業でした」と述べ、安全保障上の問題がないのか疑問を投げかけた。
小野田議員は岸田文雄政権で経済安全保障担当大臣を務めた高市氏の応援リーダー的存在。高市氏が新総裁に選出されると、この発言がSNSで拡散された。
ソフトバンクGが出資、中国では圧倒的シェア
各議員の投稿した動画を基に掃除ロボットのメーカーを調べたところ、衆院議員会館で稼働しているのは上海高仙自動化科技発展(Gausium、ガウシウム)の業務用ロボット掃除機「Phantas(ファンタス)」だった。

ファンタスは中小規模の商業施設やオフィスビル向けに設計され、吸引、掃き掃除、乾拭き、水拭きの四つの機能を持つ。高度な人工知能(AI)で歩行者や障害物を避けるのも得意だという。日本国内では、ソフトバンクロボティクス、楽天モバイル、大塚商会、アイリスオーヤマなどが法人向けに同製品を取り扱っている。
ガウシウムは2013年設立。マッピングに強みを持ち、中国では業務用掃除ロボットの9割のシェアを持ち、70カ国・地域以上に展開する。2021年11月にはソフトバンク・ビジョン・ファンド2などが主導するシリーズCで1億8800万ドル(約285億円)を調達した。
ソフトバンクグループは当時、「ガウシウムは業務用清掃ソリューションに革命を起こすと確信している」と評価し、同社のグローバル市場開拓で提携するとコメントしている。
その後、ガウシウムはソフトバンクロボティクスと日本の展示会に共同で出展するなど日本市場開拓を進め、昨年、日本市場の販売スタッフの募集を始めた。
業務用掃除ロボットは中国企業のシェアが高く、予算や機能のバランスが優れているため、中国以外のメーカーの製品を探すのは簡単ではない。ニトリホールディングスも店内清掃にロボット掃除機を導入していると報じられたが、日本経済新聞の画像をみる限り、衆院議員会館と同じガウシウムのファンタスを使っているようだ。
同分野では、ガウシウム以外にも多くの中国企業が日本市場に積極進出している。中国市場が価格競争で利益を得られにくいことに加え、人手不足と人件費上昇を背景に日本市場でロボットの需要が高まるとみているからだ。
飲食店でよく見かけるネコ型配膳ロボットを手掛ける普渡科技(Pudu Robotics)も掃除ロボットを日本に投入し、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」などで導入されている。


大阪・関西万博は日本市場を狙う中国ロボットメーカーにとってまたとないPRの機会となり、中国パビリオンではさまざまな用途のロボットが展示された。
かつては「ルンバ」のイメージが強かった家庭用掃除ロボットも今は中国企業の独壇場となっている。調査会社のIDCによると、2025年1~6月の家庭用掃除ロボットのシェアは中国の石頭科技(ロボロックテクノロジー)が清掃ロボット全体で15.2%、室内用に限ると20.7%のシェアを有し、いずれもトップだった。2〜4位も科沃斯(エコバックス)、追覓科技(ドリーミーテクノロジー)、小米科技(シャオミ)と中国企業が占め、「ルンバ」で知られる米アイロボットは5位だった。
中国企業に押されて事業が低迷している同社は今年3月、事業継続に疑義が生じていると発表している。
文:浦上早苗
福岡市出身、早稲田大学政治経済学部卒。西日本新聞社を経て、中国・大連に国費博士留学および少数民族向けの大学で教員。現在は経済分野を中心に執筆編集、海外企業の日本進出における情報発信の助言を手掛ける。近著に『崖っぷち母子 仕事と子育てに詰んで中国へ飛ぶ』(大和書房)『新型コロナVS中国14億人』(小学館新書)。X: sanadi37
36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録









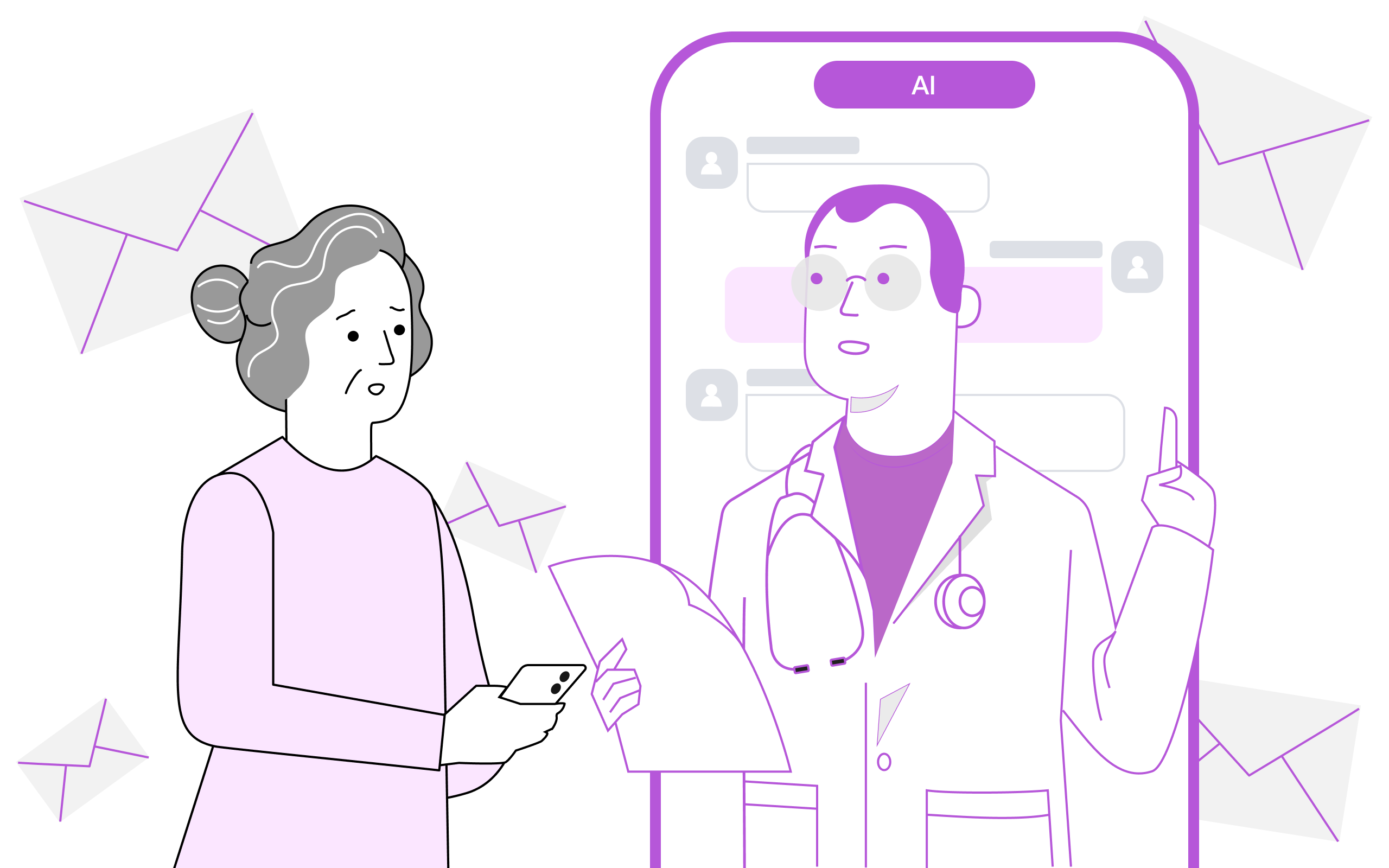

 フォローする
フォローする フォローする
フォローする