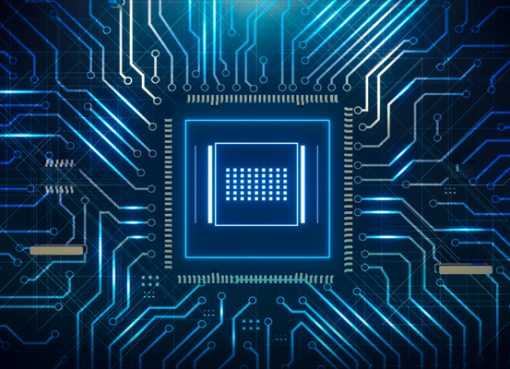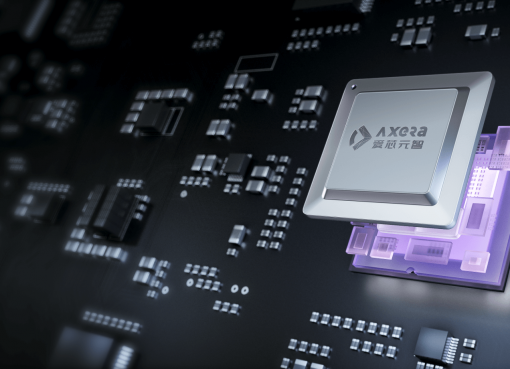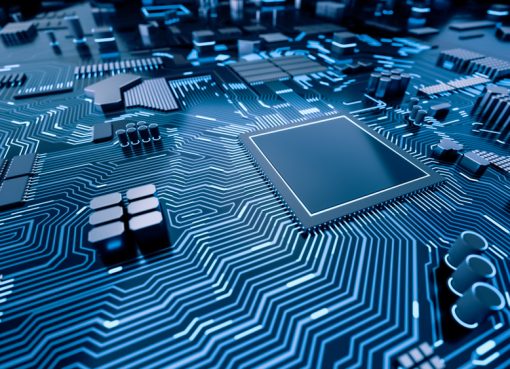セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
日本発祥のクレーンゲームは中国でも身近な存在だ。近年増え続け、増えすぎているとまで指摘されているショッピングモールによく置かれていて、カップル連れやファミリー層など若い世代を中心に人気な遊びになっている。
中国語では娃娃機(ワーワージ)と呼ばれ、直訳すると「娃娃(人形、ぬいぐるみ)を取るマシン」だ。近年はお菓子を取るマシンや、水槽内の大海老などの海産物を取るマシンも登場しているものの、クレーンゲームの景品はやはりぬいぐるみが主流で、日本のキャラクターもよく見かける。
「儲かる」クレーンゲームビジネス
中国のクレーンゲーム機市場規模は、2023年で前年比9.64%増の6億3700万元(約140億円)に達し、クレーンゲームの売上高は数百億元(数千億円)規模だという。ちなみに日本のクレーンゲームの売上高は約2810億円(2021年)となっている。中国の「数百億元規模」は極めて曖昧な数字だが、個人や小規模企業がマシンと景品を購入して設置しているので、正直なところ中国の調査会社でも調べようがない。クレーンゲームの景品もなんともB級感漂うが、これは小銭を稼ぐべく設置していることが背景にある。
中国でのクレーンゲーム生産は1990年代にさかのぼる。台湾メーカーが広東省広州市の番禺区で生産環境を整えたのが始まりだ。その影響で今も番禺はゲームセンター向け機器の生産が多い。ただ90年代にはクレーンゲームはほとんど普及しておらず、2000年代に入ってから大都市のモールや映画館などで見るようになる。
2010年代に入り、IoTやWeChat Pay、Alipayといった電子決済が浸透すると、クレーンゲームも一気に普及が進んだ。消費者はコインを準備する必要がなくなり、利用するハードルがぐんと下がった。運営側も、どの景品がより多くのユーザーを惹きつけるのかといったデータを分析できるようになった。

「これは儲かる」と考えた人々が次々とクレーンゲーム店の開業に乗り出し、機器メーカーも販売に力を入れた。ちょうどその頃、中国では「ニューリテール」が大きな話題となり、無人コンビニやガラス張りの小型無人カラオケボックスなどの無人サービスがブームになっていたことも、クレーンゲームの勢いを後押しした。クレーンゲームをショッピングモールに設置すれば、寝ていてもキャッシュレスで収益が入ってくる──そんな理想的な投資案件として、多くの人々がクレーンゲームビジネスに参入し、一気に拡大していった。
資金力にものをいわせた「咔啦酷」や「夾机占」といったクレーンゲーム専門チェーンも出てきた。咔啦酷は2017年に設立されるや3度の資金調達を実現し中国各地に店舗を展開。翌2018年には店舗数100、稼働台数は3000台にまで拡大した。
一方、消費者側では、クレーンゲームでおもちゃを獲得する様子をライブ配信する動画が話題となり、「クレーンゲームの神(抓娃娃機大神)」と呼ばれるインフルエンサーも登場。10万元(約200万円)以上を投じ、半年で3000体以上のぬいぐるみを集め、自室をぬいぐるみで埋め尽くしたという事例もあった。
スマートフォンとキャッシュレス決済の普及によって、クレーンゲームの遊び方はアップデートされ、業界全体は「お祭り状態」となっていた。
なぜ、クレーンゲーム離れに⋯
しかし、その夢のようなビジネス環境も、だんだんと消費者の熱気が冷めることで落ち着きを見せ始めた。日本ではクレーンゲーム人気が地道に続いているのとは対照的だ。
中国で続々と出てくる新しいエンタメに消費者が目移りし、クレーンゲーム離れが起きた。クレーンゲームは直訳すると「ぬいぐるみマシン」となるように、多くのマシンがぬいぐるみをつかんで取るゲーム台のままだ。つまりゲームプレイは単調で、また日本のように人気IPと提携した限定グッズがとれるわけでもない。

加えて近年ではクレーンゲームの難易度が意図的に調整され、たくさんプレイ代金を投入しないと取れないことや、何の品質認証もなくIP権利者から使用許可もない激安のぬいぐるみが景品となっていることが、何度かニュースで報じられた。とはいえ、そうした報道を知る人は一部に限られ、たとえ知っていたとしても、「それでも遊びたい」と思えるような魅力が失われていることが、クレーンゲーム離れの根本的な要因といえるだろう。

行き詰ったクレーンゲームの解決策として中国で行われているのは、プレイそのものをより楽しくする方法と、魅力ある景品を用意する方法だ。
前者では、最近のトレンドであるAI技術を導入し、利用者と音声交流しながらクレーンゲームをプレイできるというもの。後者は例えばクレーンゲーム専門チェーン「JOYMARK」は、コスパとデザインの両立を目指し、クレーンゲーム専用に自社IP「mark熊(マークくま)」を開発・展開している。POP MARTなどのグッズが1000円以上するのが当たり前の今、確かにコストを抑えながらも魅力的な限定商品を自社IPで提供するのはひとつの方法かもしれない。現時点ではあJOYMARKの店舗内だけではあるが、日本のようにクレーンゲーム景品のIP化がどれだけ進むかが、今後の業界存続の鍵となりそうだ。
(文:山谷剛史)
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録







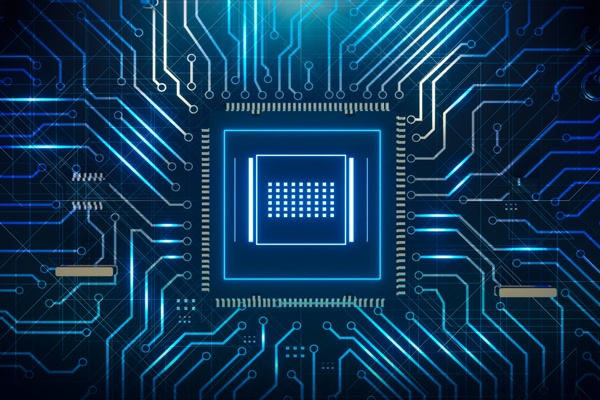

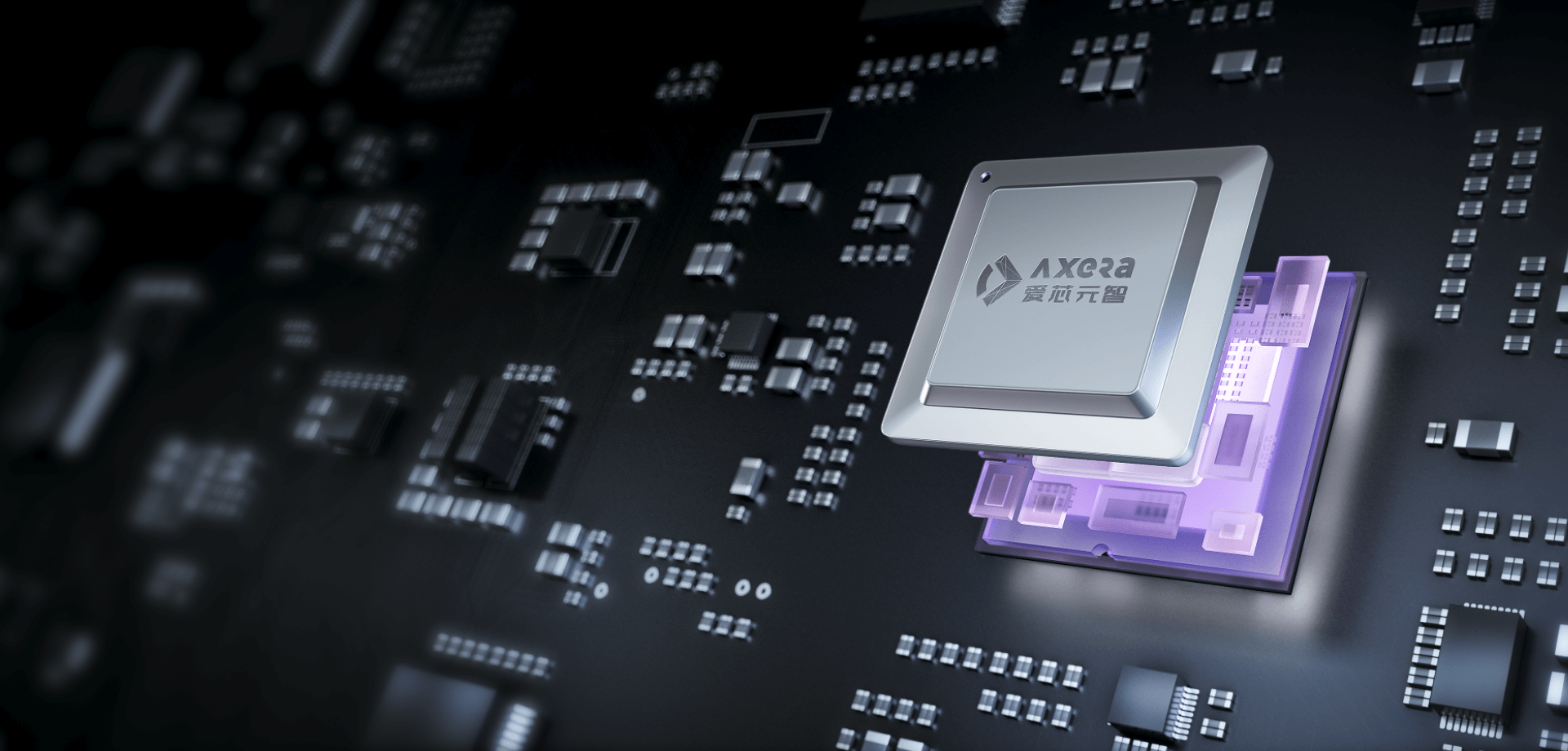

 フォローする
フォローする フォローする
フォローする