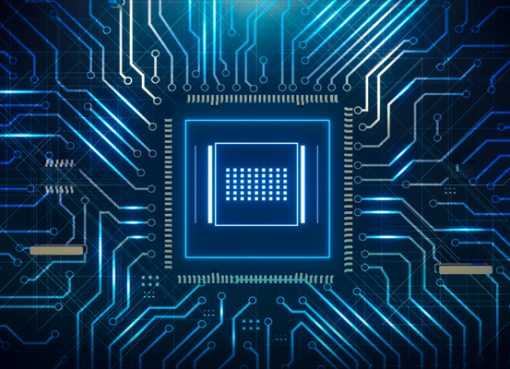セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
中国でペットといえば犬が定番だったが、今は飼い猫の数が飼い犬の数を超え逆転した。
「2023〜2024年中国ペット産業白書」によると、23年の中国で登録された犬は前年比(以下同)1.1%増の5200万匹、猫は6.8%増の7000万匹で猫のほうが増加率は高くその差は広がっている。飼い主の年齢で見ると90年代生まれと00年代生まれが半数以上となる56.7%を占め、つまり新たにペットを飼おうとしているのは若い世代が多いということであり、特に猫を飼う傾向が強いことが予想できる。家で飼われる猫のほか、中国の大都市では競争状態となっている猫カフェで飼われる猫も含まれ、店には猫を飼いたいが責任をもって飼う自信がない人や、猫に癒されたい人がやってくる。
近年の中国は少子高齢化が進み、さらに非婚化の風潮も加速している。寂しくないよう高齢者家庭や独り身の人がペットを求め、普及していくことは十分に考えられる。iiMedia Researchによると、中国における世帯でのペット普及率は23年には22%であり、米国の70%やヨーロッパの46%という普及率を大きく下回っていることも、今後さらに普及していく可能性があることを示している。
292-1024x683.jpeg)
ペットのためなら支出を惜しまない
浙江省ペット産業協会の徐会長は「人々のペット消費概念とペット経済は密接に関係している。今さまざまな新しいペットビジネスが出てきていて、ペット経済の発展を促進している」と語る。
金銭感覚が落ち着いておらず、好きなものには消費を惜しまない中国の若者が新たに飼いだしたこともあり、単価をあげても製品やサービス利用に積極的だ。上海のペットショップチェーン店で10年以上働くペット美容師は「近年、ペット愛好家の消費スタンスが明らかに変化している。今は以前よりだいぶ高くなり、1回あたり100元を超えるけれど、それでも人々のペットの手入れへの熱意がすごいと感じています」という。
犬猫を飼えば出かけるときは知り合い、ペットショップやペットホテルに預けるのが定番だったが、ペット同伴旅行を専業とする旅行社も登場。上海の旅行社は当初は近隣省への旅行が主だったが、吉祥航空のチャーター便を活用した旅行も実現。ペットを飛行機の機内に持ち込むという顧客のニーズに応えた上に、最近ではタイへの海外ツアーも行い高価ながら好評を得た。今後はバリ島ツアーやフィンランドツアーを実現したいとしている。
もう少し身近なペットフード市場についても、「2022年ペットフード市場トレンド洞察(魔鏡洞察)」によると、今はより製品カテゴリが細分化され、同時に高級化しているという。特にキャットフード、その中でも猫用おやつは急速に成長しているという。
次々と誕生する新規ビジネス
そもそもペットの販売自体もビジネスだ。中国の猫販売は路上の猫売り屋から高級ペットショップまで様々で、金を惜しまず高価な猫を飼う人もいるがもちろん出費は抑えたい人もいる。そうした人のための新たなビジネスもできている。上海や杭州などの華東を中心に展開するペットチェーン「幺社領猫館」では、無料で猫の里親になれるがキャットフードや猫砂などはその店で買うというシステムを導入。電子決済サービスのアリペイを活用し、契約後2年間は同店で毎月猫用品を購入し続けるというもので、なんだかスマートフォンを通信費だけで入手するようなシステムだ。こうしたビジネスモデルのペットショップは続々とできているといい、消費者に新たな選択肢を与えている。
「猫は飼いたいというほどでもないが、猫を見守りたい」――そんなニーズがあるのか、「街猫」という野良猫の餌やりをサポートするサービス、シェアサイクルで知られるハローバイクから出ている。WEBカメラのついた自動給餌器が様々な場所に設置され、サービス利用者は猫がやってくるのをライブ動画を通してみることができ、投げ銭をすると餌が機械から金額分投下され猫を喜ばせられるというサービスだ。したがって投げ銭が同サービスの売上になる。

さらに、餌やりを行いその様子を皆でシェアするのだけが目的ではなく、そこに猫が集まることで野良猫を去勢し、個体数をコントロールするのを狙う動物団体や個人もいる。ただ現実ではあまりに対応スタッフが少なく、猫は集まっても去勢できないという問題や給餌器がかなり汚れるという問題が出てきている。

ところでペットの寿命は人間より短く、別れの時はいつかやってくる。人気ECサイトのタオバオで検索するだけでも、ペットの毛の培養や毛や歯を使ったアクセサリー製品化、遺骨保管製品などさまざまな関連製品やサービスが表示される。ペットを復活させるためにクローン技術を使った高額なサービスを利用する人々もいる。いくつかニュースがあるが20万元(約430万円)前後かかるケースが多い。AIを活用して亡き人の見た目と声を復活させる事例はあるが、ペットについてもAIによる復活サービスはそう遠くないうちにリリースされるというのがペット記事で見る今後の予想だ。
中国国内のペットブームは中国国外にも波及することだろう。既にペット用グッズやペット用スマート機器が中国だけでなく海外でも売られていてこの動きは加速するし、AI復活といったソフトウェアも海を越えよう。またペット同伴の海外旅行が普及していけば日本も目的地となり、日本での受け入れ場所がチャイナマネーを取り込むことになる。猫が自慢の島や集落で、投げ銭リモート餌やり器が出てきてもおかしくない。
(文:山谷剛史)
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録








中国の科学者、拍動で発電するペースメーカー開発XxjjpbJ000058_20260127_CBPFN0A001582.jpg)


 フォローする
フォローする フォローする
フォローする






中国の科学者、拍動で発電するペースメーカー開発XxjjpbJ000058_20260127_CBPFN0A001582-510x369.jpg)