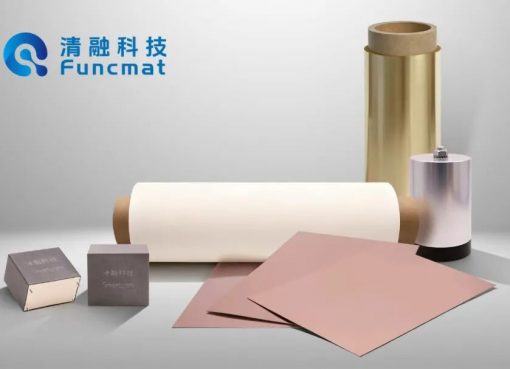原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
トヨタ自動車の中国法人、トヨタ自動車(中国)投資(Toyota Motor (China) Investment、TMCI)が業績に厳しさを増す中で、人事改革を断行中だという。
36Krの関係者によると、2025年の年明け後に、TMCIで初となる中国人の社長に李暉氏を任命しただけでなく、広汽トヨタ(広州汽車集団との合弁会社)の藤原寛行社長を一汽トヨタ(中国第一汽車集団との合弁会社)の社長に配置換えしたことが従業員の注目の的となった。
「広汽トヨタの社長が一汽トヨタの社長になる人事異動は珍しい」 と事情に詳しい人物が語った。また、江蘇省常熟市にあるトヨタ知能電動車研究開発センター(IEM)の王君華副社長も、一汽トヨタに加わることになるという。
さらに、トヨタはより詳細な事業統合を考えているとみられる。 内部での消耗戦を回避し、中国国内市場の競争に備えて経営資源を統合するためだ。
事情に詳しい情報筋によると、トヨタは中国での 「ツインモデル」戦略を改善する計画だ。現在、既に初期段階の方向性を打ち出している。製品面からは、ツインモデルの一部を統合し、将来的にはどちらか一方だけを残して販売する可能性があるという。
ツインモデルはオリジナルから2種類の車種を製造する手法を指しており、例えば 広汽トヨタの「レビン(Levin)」と一汽トヨタの「カローラ(Corolla)」、広汽トヨタの「カムリ(CAMRY)」と一汽トヨタの「アバロン(Abaron)」の組み合わせとなる。 これらの車種は統合後、一汽トヨタと広汽トヨタの両社のディーラーによる共同販売をし、利益は分配される。
ツインモデルの統合に関する情報について、一汽トヨタは36Krの取材に対し「現在、そのような計画はまったくない」と否定した。
中国市場の死守が急務
トヨタ自動車は2021年に中国での販売台数が194万台となり、9年連続で最多記録を更新した。 このころから、中国の電気自動車(EV)などの新エネルギー車や独立系ブランドが急速に成長し始め、トヨタの中国での販売は下り坂に入った。 2024年のトヨタの中国での販売台数は177万6000台と低迷した。
トヨタで最も人気のあるミドル級セダンであるカムリを例に見てみると、2016年に発売された8代目カムリの販売台数は、5年連続増となり、2022年と2023年にはミドル級セダンの市場販売台数のチャンピオンとなった。 2024年3月、カムリ9代目モデルを発売し、その後2ヶ月間で9136台の受注を獲得した。ただ、2024年のカムリの中国市場での販売台数はわずか15万8000台で、前年実績の22万5000台に比べて半減に近いところまで落ち込んだ。
一方で、同時期に発売された比亜迪(BYD)の「秦L」は、7ヶ月で22万台以上を売り上げた。 カムリと比較して、プラグインハイブリッド車(PHV)の秦Lは、燃費、馬力、インテリジェント化された装備で、より魅力的な選択肢となっているようだ。さらに、9万9800元(約210万円)からという手頃価格で、秦Lがカムリからミドル級セダンの販売台数で首位の座を奪った。
販売台数を増やすために、トヨタは昨年、伝統的な自動車メーカーがとる通常の「値下げ戦略」を採用し、局面を打開しようとしていた。しかし、こうした方法は長期的な解決策にはならない。
経営資源の統合は、多くの自動車メーカーの選択肢のひとつとなってきた。 例えば、「マルチブランド戦略」を17年間も進めてきた中国自動車大手の吉利汽車(Geely Automobile)は、2つのサブブランド「極氪(Zeekr)」と、ボルボ・カーズとの合弁ブランド「領克(LYNK&CO)」を合併し、拡大戦略から資源配分を改善して安定成長に向かおうとしている。日本においても、日産自動車とホンダは、販売台数の減少と経営課題の解決に共同で立ち向かうために合併すると発表した。
トヨタはまた、中国市場向けに特化した技術と製品を投入している。 トヨタは常熟市にIEMを設立し、インテリジェント化や電動化技術の研究開発を主な任務としている。
新たにTMCIの社長に就任した李暉氏も最近、2025年からトヨタは中国に独自の研究開発システムを構築すると述べた。
トヨタは中国市場でより野心的な目標を計画している。2030年までに中国での年間生産台数を250万~300万台にすることを目指しており、2024年の販売台数の177万6000台に比べて80%近く増加することに相当する。
*1元=約21円で計算しています。
(36Kr Japan編集部)
原文はこちら
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録







世界初のハイブリッド大型無人輸送機、重慶で初飛行に成功XxjjpbJ000175_20260203_CBPFN0A001986-scaled.jpg)




 フォローする
フォローする フォローする
フォローする
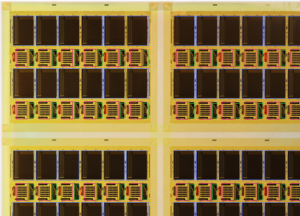



世界初のハイブリッド大型無人輸送機、重慶で初飛行に成功XxjjpbJ000175_20260203_CBPFN0A001986-510x369.jpg)