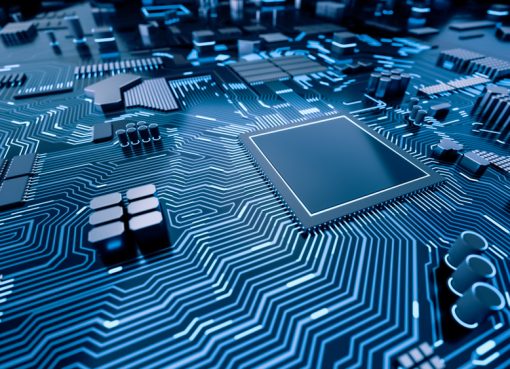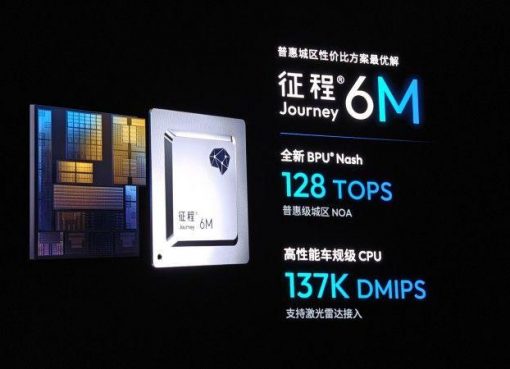セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
中国では「中流階級(ミドルクラス)が貧困層に逆戻りしている」との声が上がっている。確かに近年、中流階級の資産は目減りし、雇用機会も減少傾向。普段ネガティブな話題を控えがちの中国メディアでさえもこの現象を報じるほど、社会の共通認識となっている。
政府はスマートフォンや電気自動車(EV)の買い替え促進政策で消費を促す一方で、中国企業の多くは国内市場に対し過剰に期待を抱かず、国外展開に活路を見出そうとしている。中国で一定以上所得層は日本ブランドを好んで購入する傾向もあり、日本としても中国の不景気は他人事ではない。
では、中国の中流階級で何がおこっているのか?貧困化は本当なのだろうか。中国メディア「青年志」では専門家を招いて討論し、現状を分析している。これはなにかと中国を先行した日本にも通じるものがあるので、参考になる点も多い。
中国における「中所得層」とは誰か
中国の中流階級は2010年以降に一気に増えている。所得が上がり続けて、衣食住に余裕ができ、高等教育を受けた人々が増え社会人となり、娯楽や文化に対する消費も広がった。経済的な指標に加えて、教育や職業、多様な消費行動といった社会学的要素が「中流」を形づくってきた。
中国の第14次5カ年計画の概要で「中所得層」という用語の説明があり、「中所得層とは、安定した収入があり、家庭も裕福で生活にゆとりがあり、社会の発展水準に見合った消費水準やライフスタイルを有する層」だと書かれている。また、国家統計局の「家計収支生活状況調査」によれば、年収10~50万元(約190万円〜950万円)の世帯は、全国で約1億4000万世帯あり、中所得層全体では4億人超としている。
民間企業の定義では、しばしば胡潤研究院が引き合いに出される。胡潤「2019年中国新中流階級白書」では、中流階級について一線都市で年間世帯収入が30万元以上、新一線都市以下で20万元(約380万円)以上と定義している。前述の公式統計よりもかなりハードルが高く、公式の経済的観点から見ても社会学的観点から見ても、高所得層に入るとしている。
一方で社会学的には、「肉体労働をせず、十分な収入があり、ある程度の余暇と購買力を持つ人々」が中流階級に分類される。2010年にはすでに中流階級は人口の約20%を占めているという説があり、現在では40%程度と推定されている。
「逆戻り」の実態——数値で見えにくい体感的な貧困
国家統計局によれば、総所得から所得税や社会保障などを差し引いた可処分所得は、増加している。つまり所得は上昇し続けているので、それを見ると中間層全体が貧困化しているとはいえない。しかし、生活者が実際に使えるお金は、住宅ローン、自動車ローン、子どもの教育費、毎日の通勤費などの固定支出を差し引いた後の金額に左右される。収入が増えても支出がそれ以上に増えれば、「貧しくなった」「生活が苦しくなった」と感じるようになるわけだ。
それでもかつては、給料は年々大きく上がり、企業は成長の一途で、誰もが投資すればそれ以上で回収できてうまくいく時代はよかった。2000年代以降、中国では外資系企業やIT・金融業が台頭しそこに入った人は財を得た。しかし外資系企業の社員はピーク時の約3000万人を頂点に、2023年には2000万人まで減少し、IT企業も近年大規模なリストラを進め、高給取りも例外なく急に仕事を失う危機に直面している。同時に、多くの若者は不動産が高い2010年代に住宅を購入し、ローン返済に追われる生活を送っている。その上で景気の先行きも不透明で、仕事が不安定な状況にあるため、経済的なプレッシャーが中流層をじわじわと圧迫している。
中国のネット上で「返貧三件套」」「返貧五件套」(貧困逆戻り三点セット/五点セット)というネット用語まで出てきている。3点セット5点セットの定義は書かれている文章により異なり曖昧だが「不動産」「子どものエリート教育」「失業」「無計画な起業」「盲目的な投資」あたりが主に挙げられる。まさに中流層の不安定化を象徴している造語だ。
「中流らしさ」は金額でなく、ライフスタイルに
中流階級の特徴として、「社会の発展水準に見合ったライフスタイル」も重要視される。
中国経済は急激に成長し、かつてはブランドの服や車、パソコンなどの「モノ」によって身分をアピールしていたが、近年の消費の焦点は「外見上のステータスシンボル」から「ライフスタイル」や「精神的充実(マインドフルネス)」へと移りつつある。
その傾向は、中国版インスタグラムと称されるSNS「小紅書(RED)」の人気コンテンツからも明らかだ。アパレルではなく、飲食、旅行、教育、アウトドア、スポーツといった「コト消費」が主流になっている。
またアニメ・ゲームとその派生商品(二次元)やアイドルといったサブカルチャー消費も今までにない消費も台頭している。前のように共通する服や車などの物差しで差別化する時代は過ぎ去り、自身の趣味趣向でアイデンティティを表現する時代になっている。
その結果として、中国の消費者は「こだわりのない」ところでは、合理的にダウングレードし、コストパフォーマンスを重視する傾向を強めている。たとえば外食ではサイゼリヤ、アパレルではユニクロなど、品質と価格のバランスに優れたブランドが人気だ。また、ECプラットフォームの淘宝(タオバオ)などでは、格安商品で「モノ欲」を満たすことが一般化しており、欲しいブランドがあれば、OEM元の商品を探してより安く入手するという消費行動も珍しくない。
旧来のモノ消費は都市部で抑えられる一方、農村部でネットや物流インフラがの整備が進み、都市部の中流階級と同等の消費ができるようになっている。
まとめてみれば世帯年収10万元以上ならば中流階級だが、中国のバブル時代の先行投資の債務が足を引っ張り、多くの人が「逆戻りの不安」を感じている。また今の中流階級の消費スタイルはもはや支払った金額の大小で決まるものではなく、自分の趣味趣向に満足できる消費ができていれば、それこそが「新中流階級」となる。今後の中国では、こうした価値観がより広がっていくかもしれない。
(文:山谷剛史)
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録






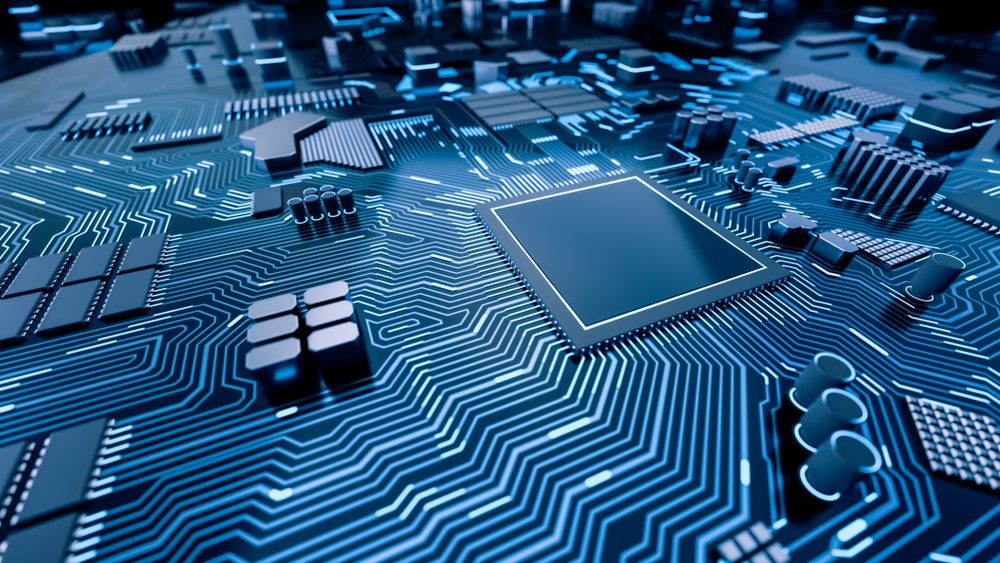




 フォローする
フォローする フォローする
フォローする