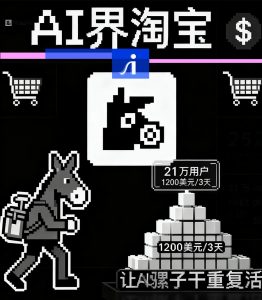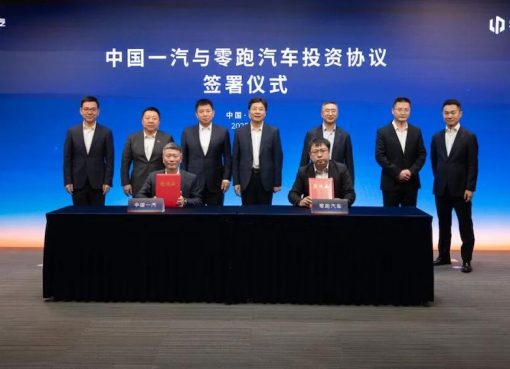セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
過去10年間、ドローンのDJI(大疆創新)を皮切りに、モバイルバッテリーのAnker(安克創新)、3DプリンターのBambu Lab(拓竹科技)、ポータブル電源のEcoFlow(正浩創新)など、深圳発の新世代ハードウエア企業が相次いで台頭した。共通するのは、海外市場での強さで、36Kr Japanでもそういった企業や製品を数多く取り上げてきた。
かつて、投資家の関心は中国のネットサービスやコンシューマ向けアプリなどに集まっていたが、現在はハードウエア分野に移りつつある。ある投資家は36Krの取材に対し「良質なハードウエアプロジェクトへの参入ラッシュがすごい。今、海外向けに注目しなければ、取り残される」と語る。
資本の流入は人材獲得・研究開発(R&D)・市場開拓を加速させる。結果として、深圳発企業のグローバル存在感はさらに高まっている。そこで、最新の状況を踏まえつつ、深圳という街の特殊性を紹介したい。
「DJI効果」ー最初の成功が作った規範
ドローン大手で知られるDJIは、電子部品の集積地である深圳・福田区の「華強北」ではなく、西南部の南山区に本部を置く(2006年設立)。2014年にウォール・ストリート・ジャーナルより、「世界の主要消費者製品カテゴリーで先駆者となった最初の中国企業」と紹介された。当時、ドローン市場をけん引していたのは米3D Roboticsだった。その後、DJIは安定して世界のコンシューマ向けドローン市場の70%以上のシェアを獲得。莫大な収益と高い利益率といった経済的成功だけでなく、「二番煎じで低利益」という中国製品の悪しき常識を覆した。
3D Roboticsの創業者で、かつてWired誌の編集長を務めていたChris Anderson氏は同年「DJIは21世紀に我々が対処すべき中国企業の第一波であり、その実行力は完璧だ」とコメントしている。また元DJI北米拠点責任者で後に3D Roboticsの最高販売責任者(CRO)となったColin Guinn氏もまた「ソフトウェア中心のシリコンバレー企業が、中国の強力な垂直統合型製造企業と競争するのは難しい」と伝えた。3D Roboticsはやがてコンシューマ向け市場から撤退した。
深圳で起きるイノベの循環

どの業界であれ中国企業が一度海外で成功を収めると、次々に後続を呼ぶ。
DJIの世界的ヒットを機に、南山区のあるハードウエア創業者は「かつて中国企業は高価格設定を恐れ、その能力もなかった。しかし今では、高価格を正当化できる実力も勇気も備わっている」と述べる。
実際、Bambu LabやEcoFlowをはじめ、南山区の西麗・桃源・粤海一帯にはユニコーンが20社規模で集積し、(合計で)700億ドル超の評価額に達するとされる。Bambu LabとEcoFlowに共通するのは、DJIの世界的成功に感化され、DJIを去った社員が立ち上げた企業だ。
Bambu Labは、DJIのコンシューマー向けドローン部門の責任者を経て36歳となった陶冶氏が設立した企業だ。「人生で大きなことを成し遂げる最後のチャンスだ。若さが失われていくのを感じているので賭けに出る」と創業を決意した。研究開発を重ねて多色印刷や高速造形(従来比70%短縮)を実現した3Dプリンター「Bambu Lab X1」などをヒットさせた。
EcoFlowもまた、DJIのバッテリー研究開発部門責任者だった王雷氏は、元同僚を連れてDJI本社から900メートルの場所で創業した。主力のポータブル電源「DELTA 1300」は、充電について競合他社では8時間かかるところを1時間半余りで完了するという圧倒的アドバンテージでヒット商品に。
こうしたスピンアウトの連鎖が、深圳(特に南山区)をハードウエア起業の震源地へと押し上げた。
スマホ・サプライチェーンが背中を押す
DJIが深圳のハードウエア業界に大きな刺激を与えたのは確かだが、成功のためにはやる気と資金のほかに「部品」が必要だ。近年は、掃除ロボットの技術を応用した芝刈りロボット専業のMAMMOTION(これもまたDJI出身者が創業)や、プール清掃ロボットの専業企業など、多様なスタートアップが登場している。これらの製品にはデュアルバンドチップやNPUなど様々な高度部材が欠かせない。
これがまたタイミングがよかった。深圳北部から隣接する東莞にかけてファーウェイ、OPPO、vivo、Honor、スマートフォンを量産するフォックスコンといったスマートフォンの基幹パーツを生産する企業がこのエリアに密集している。スマートフォン業界の激しい競争の結果、サプライチェーンの基幹部品も安く入手できるようになった。たとえばデュアルバンドチップやNPUといった、当初は高価だったチップが安くなり、ロボット掃除機から派生した芝刈り機など新カテゴリへの横展開が進んだ。結果、先行する欧米企業の3分の1以下の価格で提供された。
かつて深圳は、サプライチェーンを駆使し「作れるものは何でも売る」低価格競争の街だった。しかしこの5〜6年で、一部の起業家は海外市場の需要に本気で向き合い、ニーズ起点の製品開発へと舵を切った。いまや深圳は、技術力・製品力・人材・サプライチェーン・資本を束ねた総合力で、世界のモノづくりの拠点へと進化している。
(文:山谷剛史)
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録






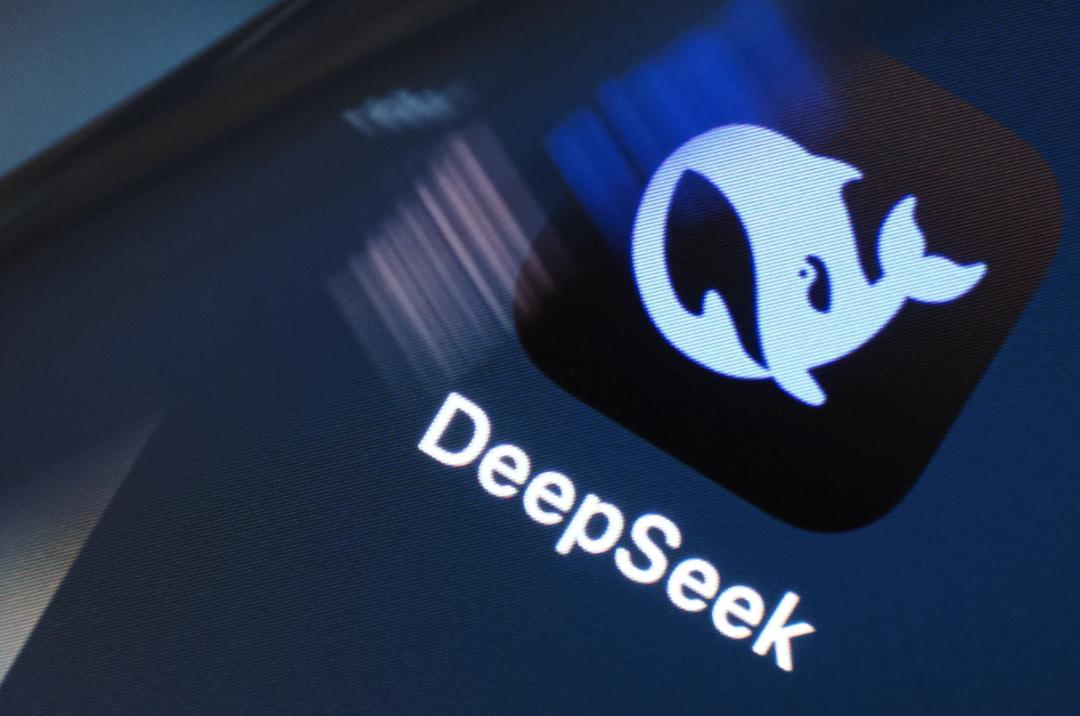
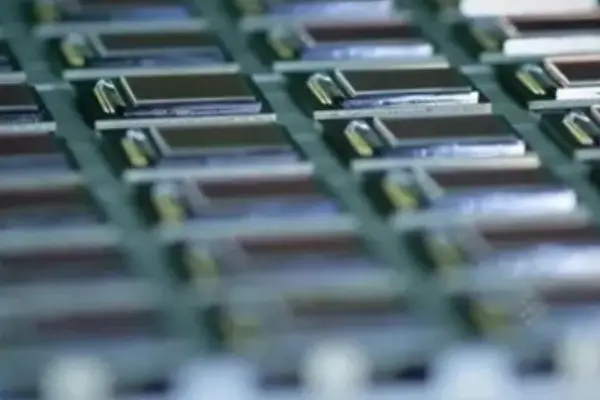



 フォローする
フォローする フォローする
フォローする